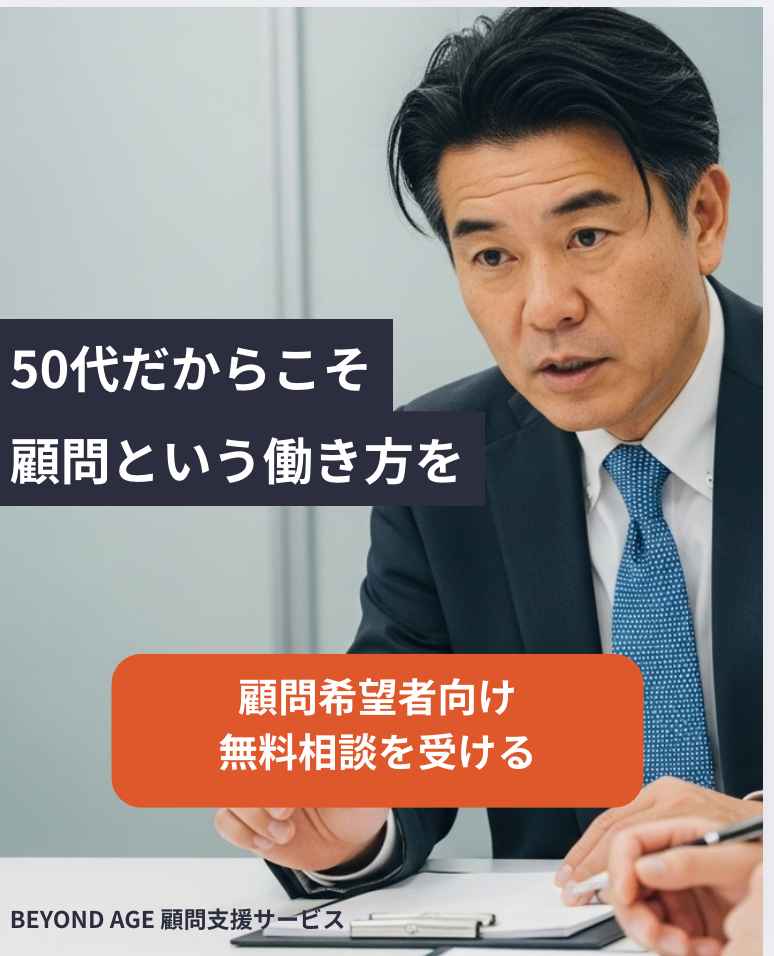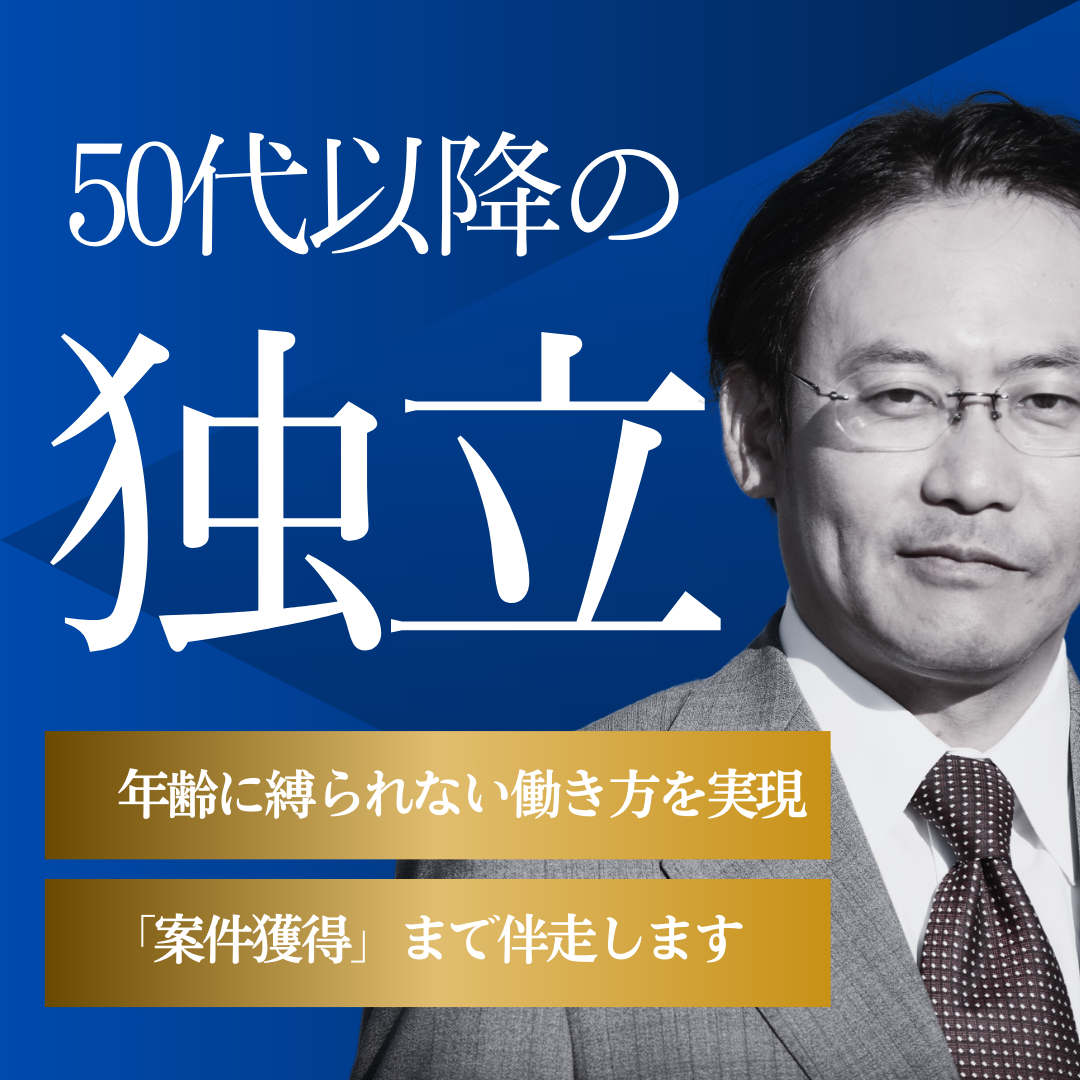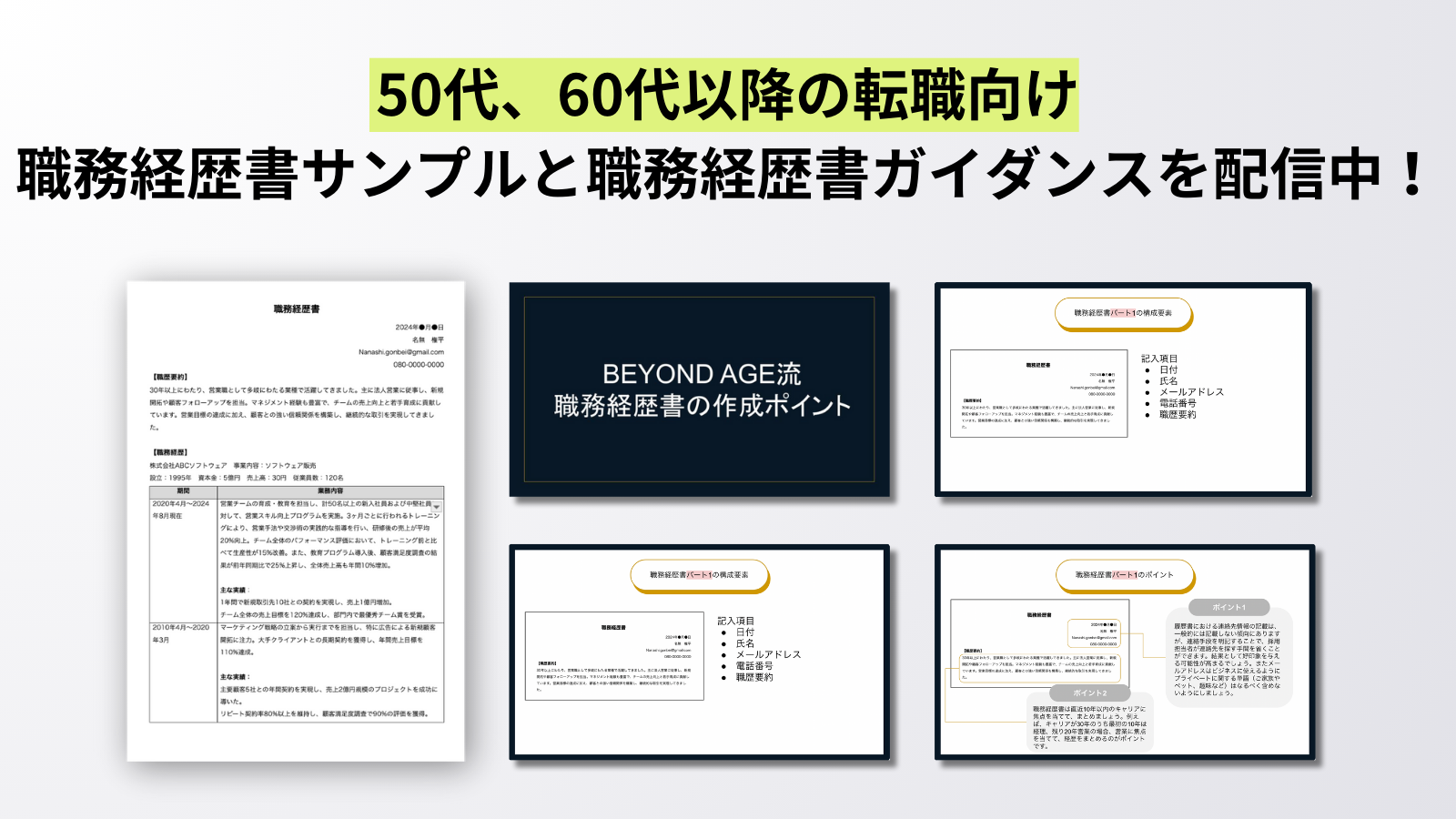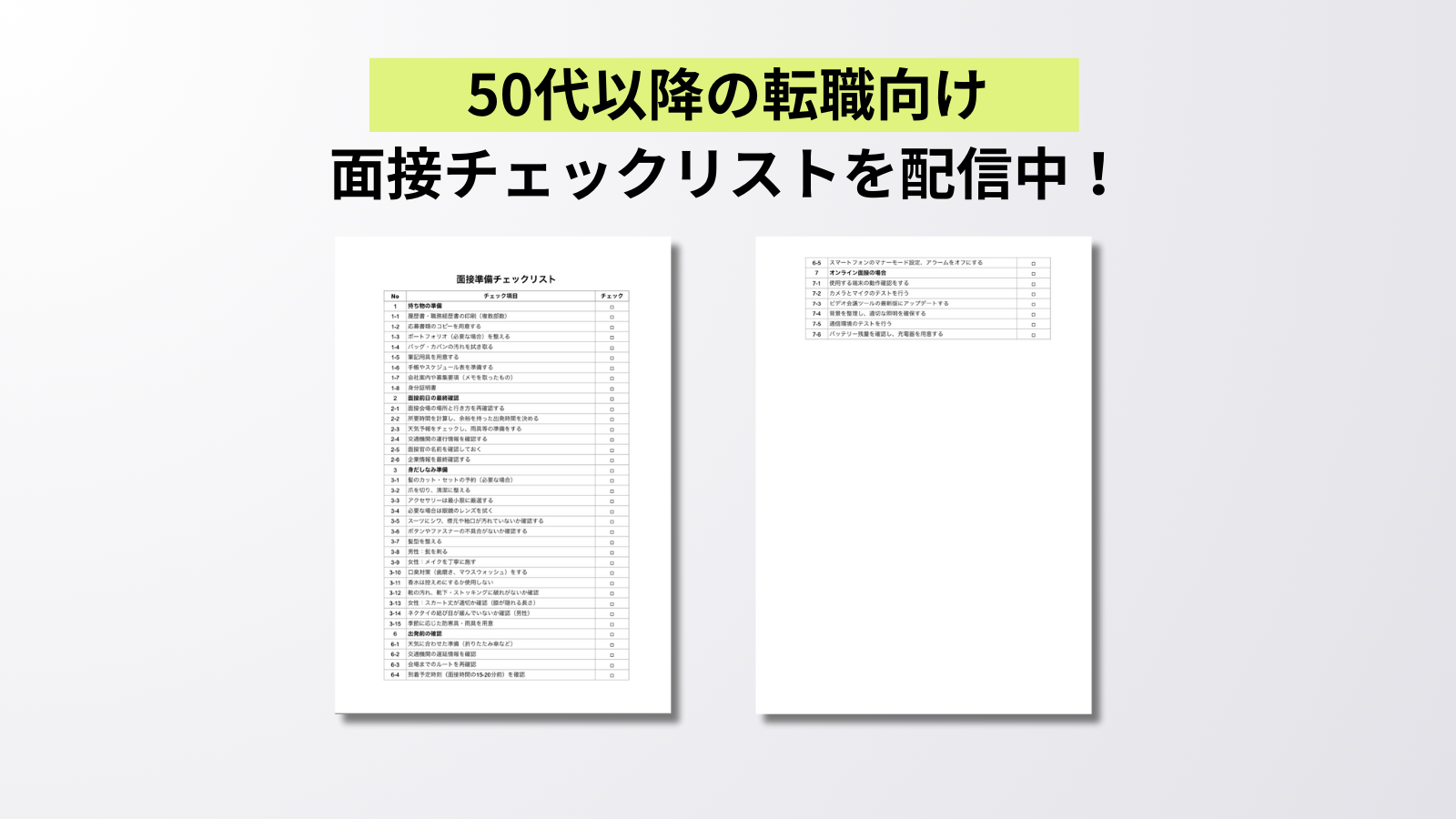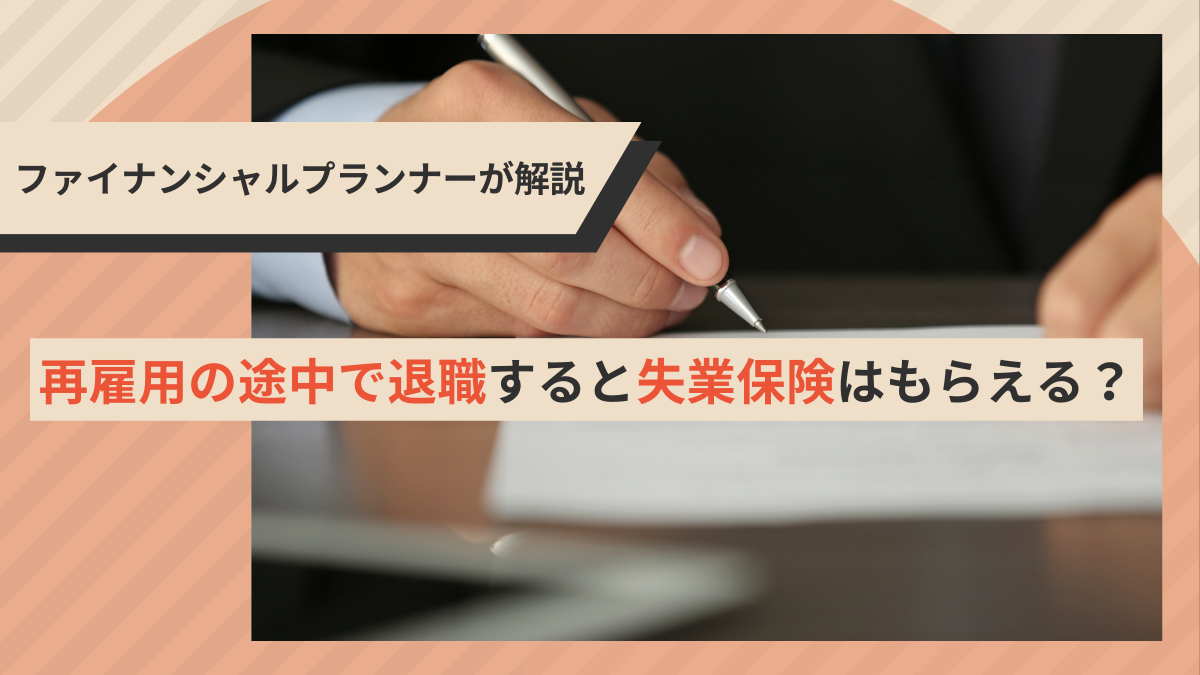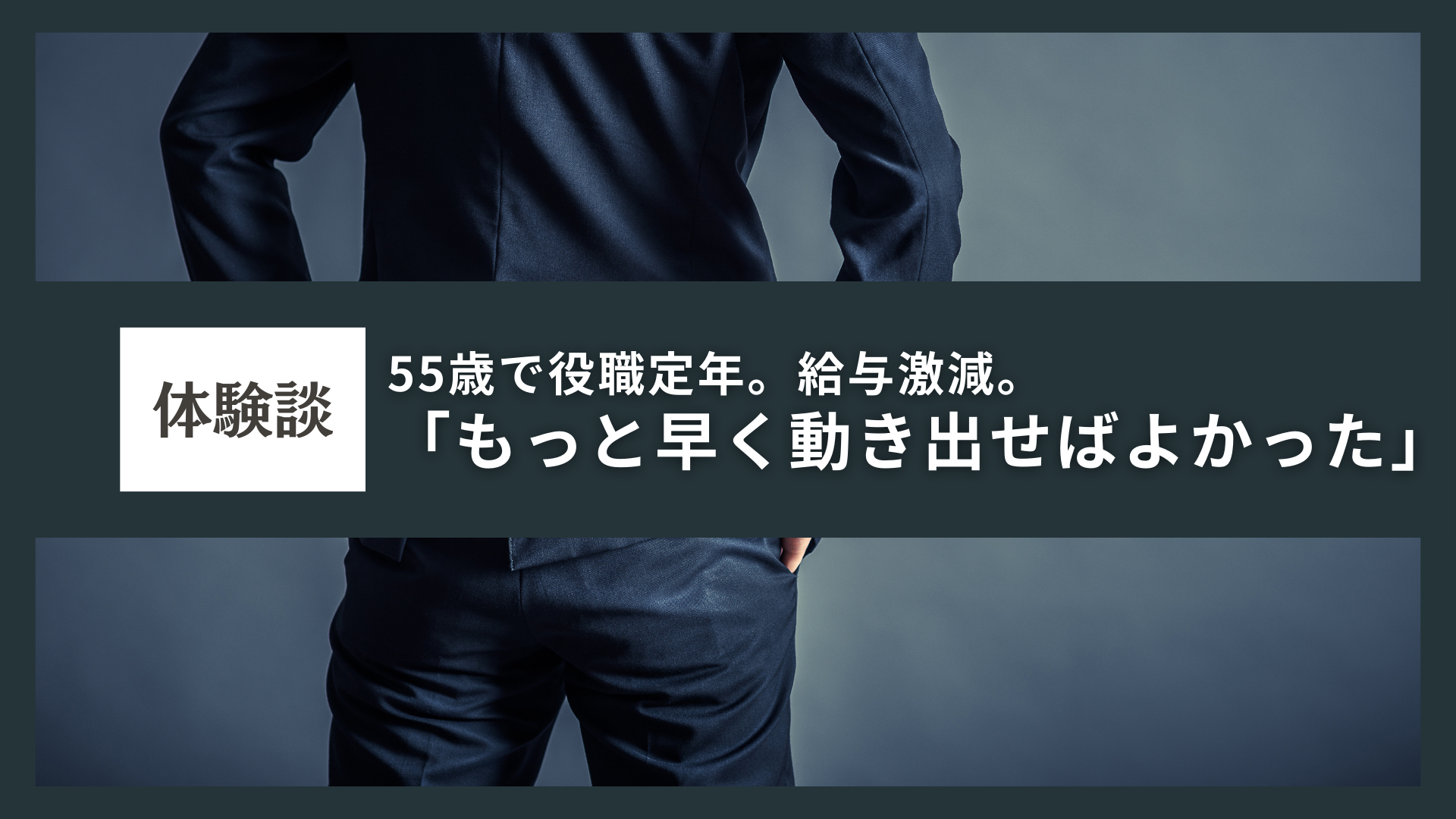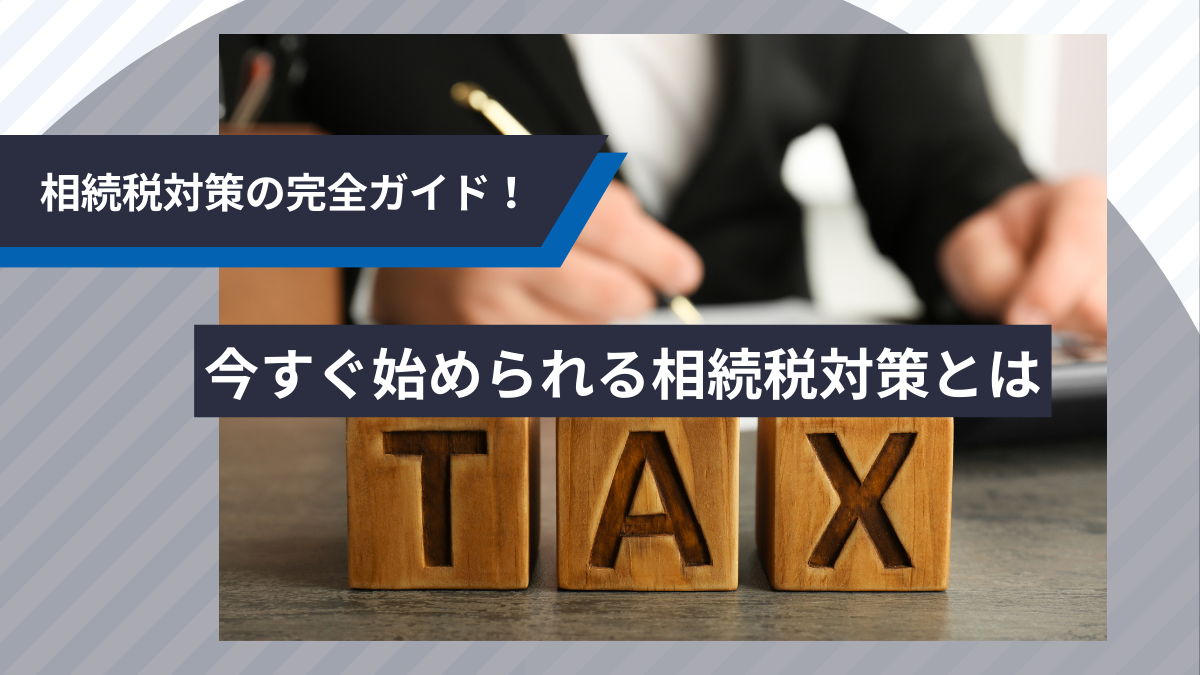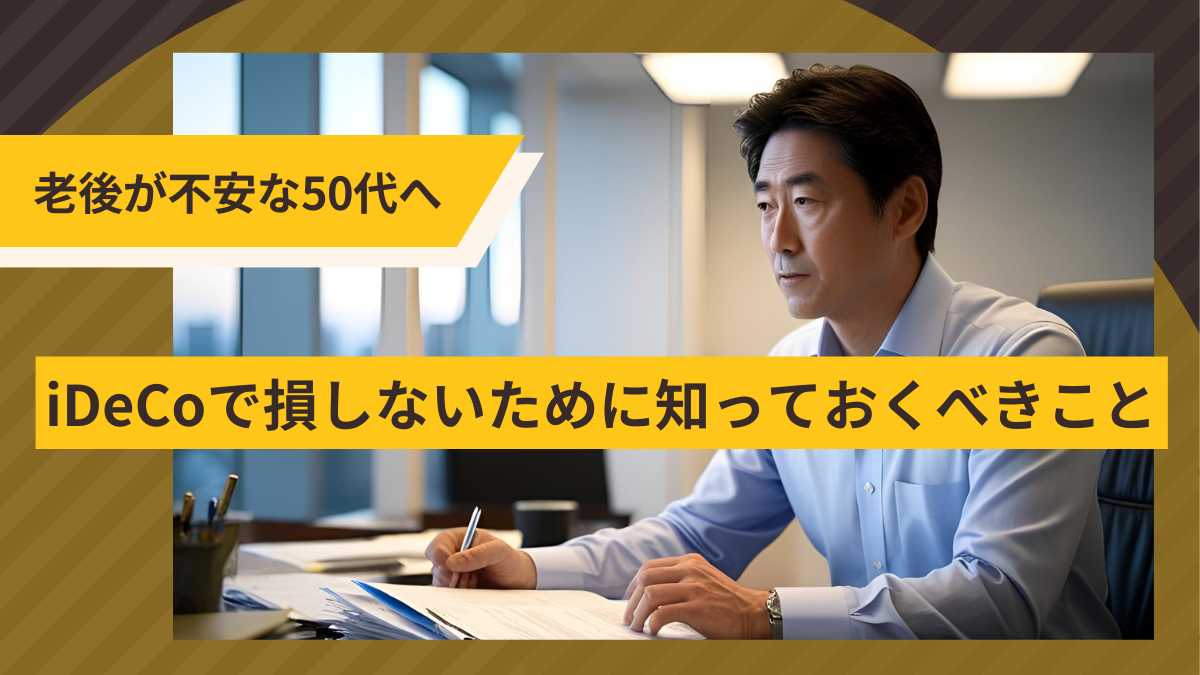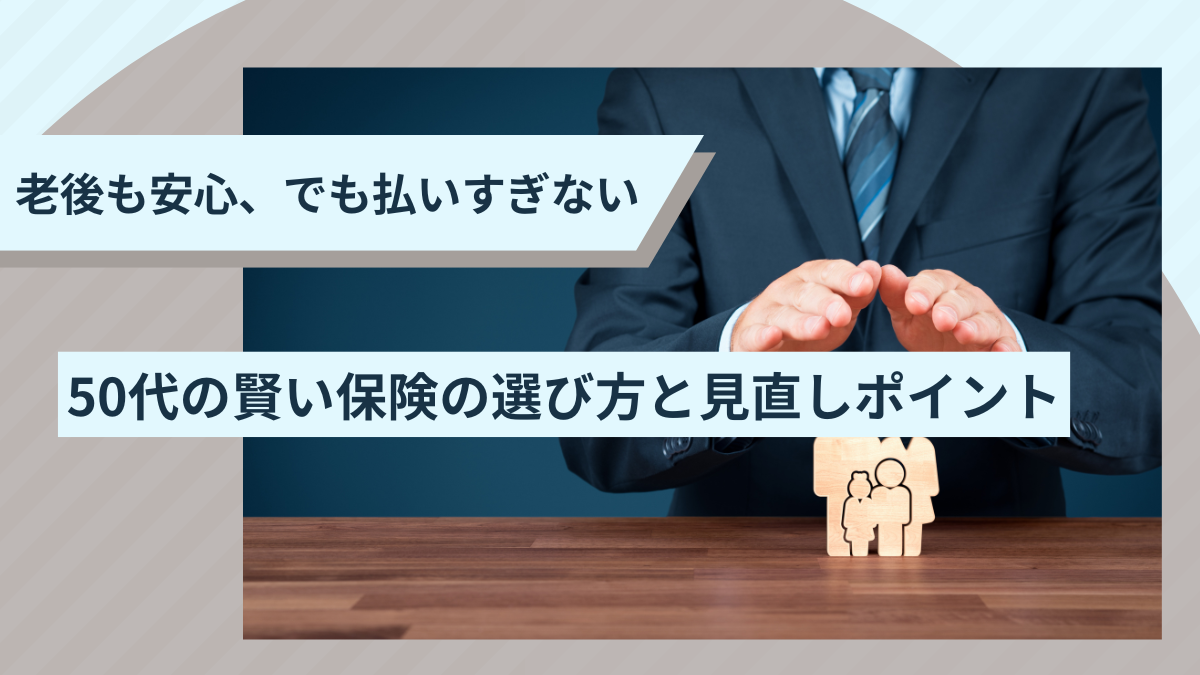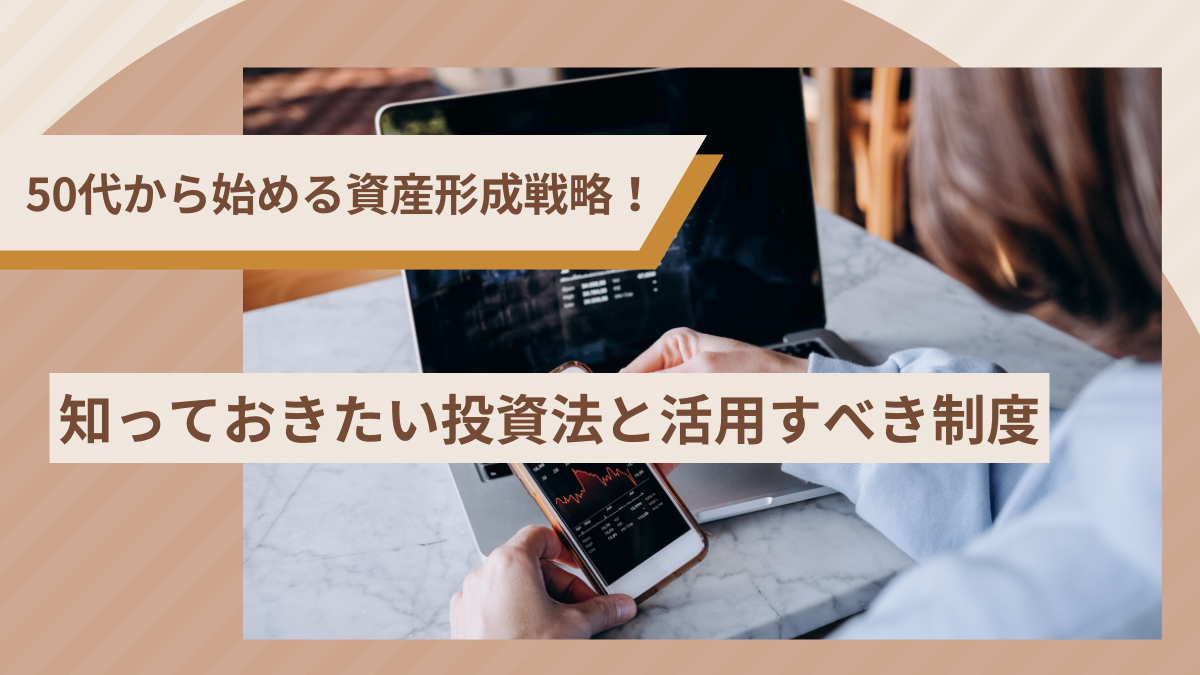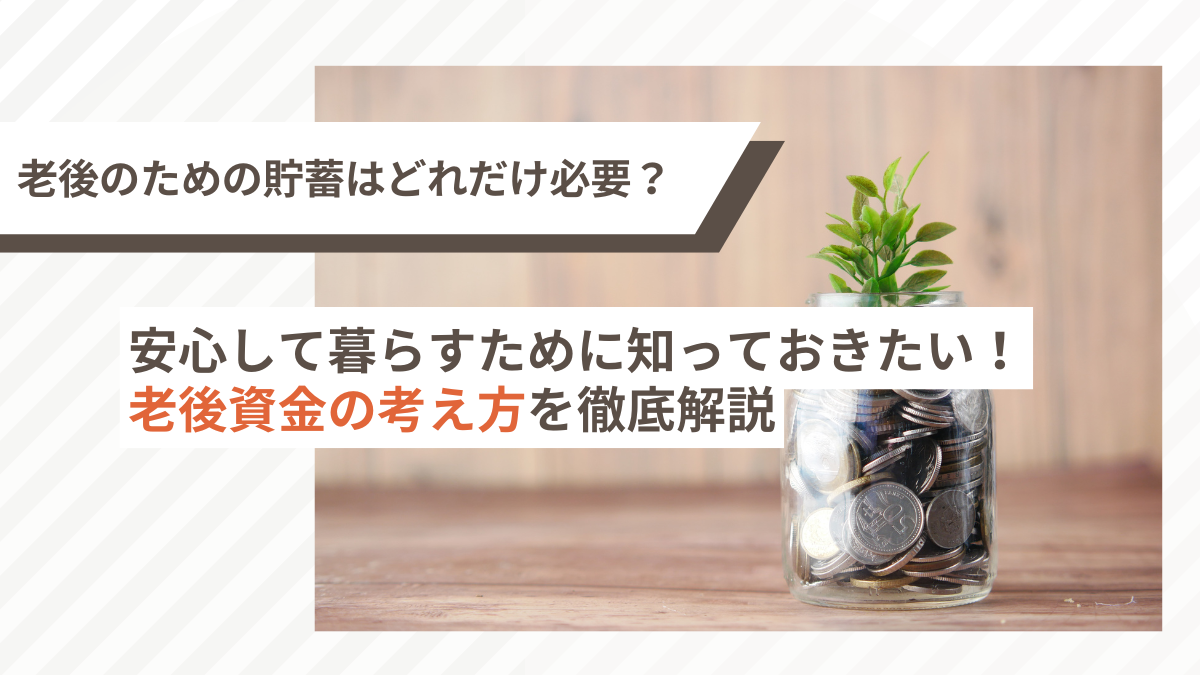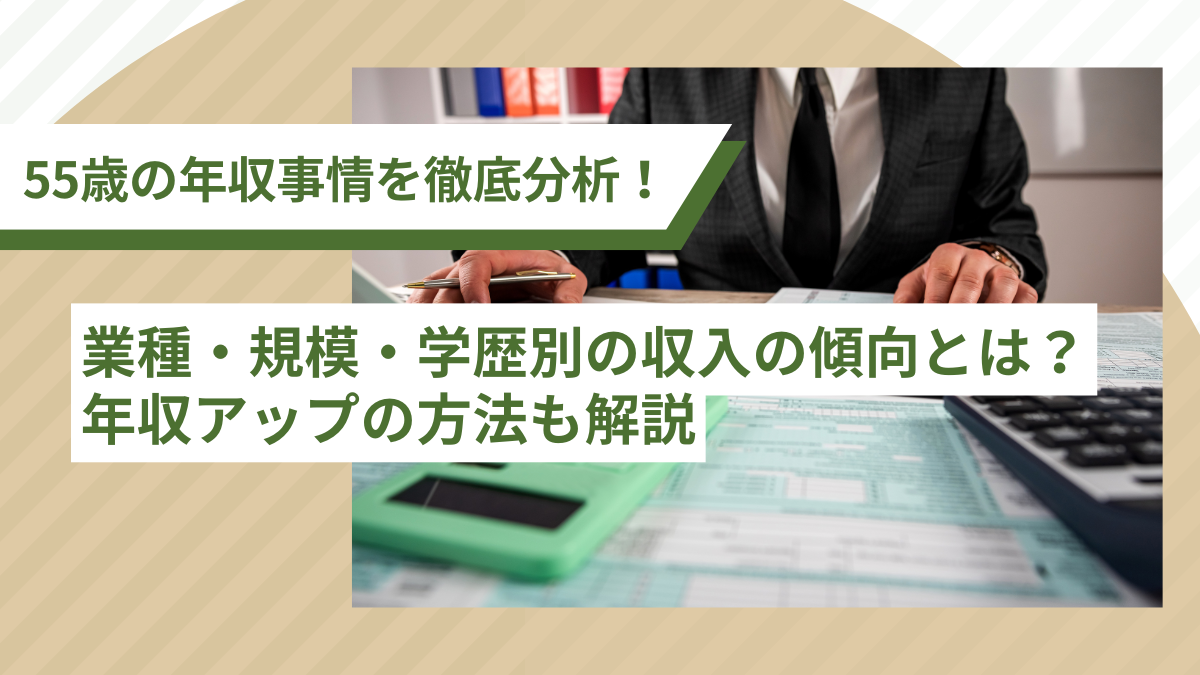55歳からiDeCoや新NISAを始めたいけれど、どちらの制度を使うべきかわからない人も多いのではないでしょうか。また、50代でiDeCoや新NISAを始めることに対して、スタートする時期として遅すぎないかと不安を感じる人も多いでしょう。
日本では「人生100年時代」と言われ、年金生活が長くなる傾向があるため、老後の資金を少しでも多く準備する必要があります。
しかし、日本は低金利が続いており、預金で資産を増やしながら貯めていくことが難しいのが現状です。
このようなことから、リスクはあるものの、元本保証ではないため『増やしながら貯める』ことができるiDeCoや新NISAに注目が集まっています。また、さまざまな税の優遇があるため、資産運用を始める人が増えています。
この記事では、「55歳からのiDeCoと新NISAはどちらが良いか」ということについて、さまざまな情報をもとに、くわしく解説します。

50代以降の転職でお困りの方はBEYOND AGEまでご相談ください
iDeCo・NISAは55歳からだと遅い?

iDeCoとNISAを始めるのは、55歳からでも全く遅くはありません。
55歳から始めても年金受給開始の65歳までの10年間で非課税で効率よく老後資金を貯められます。
また、iDeCoの受取開始年齢の上限は75歳までのため、希望すれば55歳から20年間非課税で運用が可能です。NISAは運用期間の上限がないため、55歳から何歳まででも運用を続けられます。
特にNISAはいつでも出金でき、出金額も自由に決められるという特徴があります。例えば、55歳から収入がある時は積み立て投資を続け、65歳や70歳で完全にリタイアした後は運用を続けながら、必要な分だけ資金を引き出して老後の生活に足しをするというやり方もできます。
iDeCoとNISAでは特徴やメリットが異なります。これから詳しく解説していきますので、自分に合う方法を選んで運用を始めるようにしましょう。
50代以降の転職でお困りの方はBEYOND AGEまでご相談ください
55歳からはじめるにはiDeCoと新NISAどっちがおすすめ?

iDeCoと新NISAはどちらも税の優遇があり、利用する人にメリットがある制度です。どっちの制度が良いかは、以下のように個人の状況や希望によって変わります。
| 新NISA | iDeCo | |
| 毎年一定の収入があり、所得税や住民税を減らしたい | × | 〇 |
| 好きなタイミングで資金を引き出したい | 〇 | × |
| 個別の企業に投資したい | 〇 | × |
| 投資信託に投資したい | 〇 | 〇 |
| たくさんの種類の中から好きな投資信託を選びたい | 〇 | × |
| 「金」や「REIT(不動産投資信託)」にも投資したい | 〇 | △(金融機関による) |
| 退職金を受け取る予定である | 〇 | △(退職金控除額による) |
| まとまった金額を一度に投資したい | 〇 | ×(積み立てのみ) |
| 長期で運用したい | 〇 | △(運用は最長75歳まで) |
「好きなタイミングで好きな銘柄に投資したい」「いつでも引き出せるほうが良い」など、自由度が高い投資をしたい人は新NISAがおすすめです。
毎年ある程度の所得がある人で、所得税や住民税を減らすことを優先したいという人は、iDeCoが適しています。
また、運用資金に余裕がある人は、
- 個別株式への投資は新NISA、毎月の積立はiDeCo
- 毎月1万円はiDeCo、2万円は新NISAに投資する
など、ふたつの制度を併用して分散投資するのも良い方法です。
個人事業主は、拠出金の上限が高く、iDeCoの所得控除におけるメリットが最も大きくなっているため、iDeCoの利用を検討しましょう。
それでは、iDeCoと新NISAの仕組みと違いについて、くわしくみていきましょう。
50代以降の転職でお困りの方はBEYOND AGEまでご相談ください
そもそもiDeCo・新NISAとは?

新NISAとは、国が個人の資産形成を応援するために作った税制優遇制度で、株式や投資信託などの運用益が非課税になるというメリットがあります。
通常であれば運用益に約20%の税金がかかるところが非課税になるため、運用益をすべて受け取ることができます。
例えば、運用益が100万円の場合、通常であれば約20万円が税金で引かれて手取りは約80万円となるところが、新NISAを利用した運用であれば100万円全額を受け取れる仕組みです。
iDeCoも新NISAと同様に、国が資産運用を後押しするために作った制度ですが、「iDeCoは老後の資金形成のための制度」と目的がはっきりしています。
そのため、60歳以前に資金を引き出せない等、運用における制限が新NISAより厳しくなっています。
ただし、そのかわりに運用益が新NISA同様に非課税になるだけでなく、
- 毎年1年間分の拠出金を全額所得控除できるため、所得税や住民税を減らせる
- 受け取る一時金に退職所得控除を適用できる
という、新NISAよりも手厚い税制優遇が設けられています。
iDeCoと新NISAの違いは?理解しておきたいポイント
iDeCoと新NISAにはいくつか違いがあります。どっちの制度が自分に適しているかどうかを判断する際には、2つの制度の違いをしっかり理解することが大切です。
| 新NISA | iDeCo | ||
| 成長投資枠 | つみたて投資枠 | 積み立て投資 | |
| 運用できる年齢 | 18歳以上 | 20歳以上65歳まで(条件あり) | |
| 運用期間 | 無期限 | 最長75歳まで | |
| 非課税保有限度額 | 1,800万円(成長投資枠は1,200万円まで) | 総額に制限はないが、加入資格によって毎月の拠出金の上限が決められている | |
| 運用可能額 | 240万円/年 | 120万円/年 | |
| 引き出すタイミング | いつでも可能 | 原則60歳以降 | |
| 運用商品 | 株式・投資信託・ETF | 長期の運用に適している投資信託 | ・投資信託・定期預金等 |
| 税の優遇内容 | 運用益が非課税 | ・運用益が非課税・掛金の所得控除・受取時に税金優遇あり | |
iDeCoと新NISAの違い①運用できる年齢や期間が違う
新NISAは18歳以上であれば、誰でも利用でき、資金の拠出期間や運用期間に制限はありません。80歳、90歳になっても非課税で運用し続けることが可能です。
iDeCoの加入条件は「20歳以上60歳まで」ですが、以下の条件を満たすと65歳まで加入して掛金を拠出し、運用できます。
・60歳以降も社会保険に加入しながら働く会社員や公務員(第2号被保険者)
・60歳以降に国民年金に任意加入する自営業者や主婦(夫)
65歳以降は、掛金の拠出はできなくなりますが、運用自体は最長75歳まで続けられます。
このように、iDeCoは最長75歳までしか運用できないこと、65歳以降は運用資金の拠出ができないことから、以下に該当する方は、新NISAのほうが適しているといえます。
・65歳以降も運用資金を拠出したい人
・年齢制限なく、状況に応じて長期間の運用を続けたい人
iDeCoと新NISAの違い②税制優遇が違う
新NISAは、運用益が非課税になるというメリットがあります。
iDeCoも、新NISA同様運用益が非課税になりますが、それに加えて大きな節税効果がある「掛金の所得控除」を適用できます。
所得控除とは、課税所得額から所得控除分を差し引ける制度です、課税所得を減らすことで、所得税と住民税を低くできます。
例えば、課税所得額が300万円の人が、iDeCoを年間20万円拠出した場合、課税所得から20万円を差し引けるため、課税所得金額は「300万円-20万円=280万円」となります。
このように、iDeCoによって課税所得金額が300万円から280万円に減るケースでは、以下のように税金がかわり、年間40,000円、10年間では約40万円の節税になります。
| 課税所得金額 | 所得税額 | 住民税額(所得割) | 税金の合計 |
| 300万円 | (300万円×10%)-97,500円=202,500円 | 300万円×10%=30万円 | 502,500円 |
| 280万円 | (280万円×10%)-97,500円=182,500円 | 280万円×10%=28万円 | 462,500円 |
| 1,000万円 | (1000万円×33%)-1,436,000円=1,864,000 | 1,000万円×10%=100万円 | 2,864,000円 |
| 980万円 | (980万円×33%)-1,436,000円=1,798,000円 | 980万円×10%=98万円 | 2,778,000円 |
また、所得税は累進課税のため、課税所得金額が大きいと所得税率も高くなります。
例えば、課税所得が1,000万円の人は所得税率は33%のため、同じ拠出金額でも所得控除で受けられるメリットも大きくなります。
課税所得額が1,000万円から980万円に減った場合の節税効果は、年間で86,000円、10年間で86万円の節税になります。
年収が高く、所得税率が高い人ほど、iDeCoの所得控除の効果が大きいことを覚えておきましょう。
iDeCoと新NISAの違い③運用できる金額が違う
新NISAは年間投資額の上限が「成長投資枠240万円」「積み立て投資枠120万円」と決まっています。そして、最大1,800万円(内、成長投資枠は1,200万円)まで非課税で保有できます。
1,800万円は投資元本に適用される上限です。
合計1,800万円を拠出して、運用益が300万円出ていて2,100万円が新NISA口座にあるというケースでも、投資元本が1,800万円のため、問題なく継続して運用できます。
それに対して、iDeCoでは、毎月の掛金の拠出額は比較的低く抑えられており、以下のように定められています。
| 自営業等(第1号被保険者・任意加入被保険者等) | 月額6.8万円(年額81.6万円)(国民年金基金または国民年金付加保険料との合算枠) | |
| 会社員・公務員等(第2号被保険者) | 会社に企業年金がない会社員 | 月額2.3万円(年額27.6万円) |
| 企業型DC(企業型確定拠出年金)のみに加入している会社員 | 月額2.0万円(年額24万円) | |
| DB(確定給付型企業年金・厚生年金基金・石炭鉱業年金基金・私立学校教職員組合)と企業型DCに加入している会社員 | 月額1.2万円(年額14.4万円) | |
| DB(確定給付型企業年金・厚生年金基金・石炭鉱業年金基金・私立学校教職員組合)のみに加入している会社員 | 月額1.2万円(年額14.4万円) | |
| 公務員 | 月額1.2万円(年額14.4万円) | |
| 専業主婦(夫)(第3号被保険者) | 月額2.3万円(年額27.6万円) | |
55歳からiDeCoを始める場合、10年間で投資できる額は、個人事業主を除くと最大で240万円ほどになります。
iDeCoを利用しつつ、もっと多くの資金を運用したい場合は、iDeCoだけでなく、新NISAも併用して運用すると良いでしょう。
また、個人事業主は例外的に、月額で68,000円という大きな額をiDeCoに拠出でき、全額を所得控除して所得税・住民税を減らせるという大きなメリットがあります。
これは、個人事業主は厚生年金に加入できず、老後の資金を自分で貯めなければならないためです。
個人事業主は、iDeCoの所得控除で大きな恩恵を受けられることを覚えておきましょう。
iDeCoと新NISAの違い④資産引き出しの条件が違う
新NISAは、運用資金を自由に引き出すことができます。それに対してiDeCoでは、60歳以前は運用資金を引き出せないというルールがあります。
また、iDeCoの資金の引き出しは、最初の掛金拠出から10年経過していることが条件となっています。
50歳を超えて加入する場合は、以下のように資金を引き出せる年齢が繰り下げられます。
| iDeCo加入年齢 | 受給可能年齢 |
| 50歳超~52歳 | 61歳 |
| 52歳超~54歳 | 62歳 |
| 54歳超~56歳 | 63歳 |
| 56歳超~58歳 | 64歳 |
| 58歳超~60歳 | 65歳 |
| 60歳超~64歳 | 加入から5年を経過した日 |
55歳からiDeCoを始める場合は、60歳ではなく、63歳以降でないと資産を引き出せないため注意しましょう。
iDeCoと新NISAの違い⑤運用商品が違う
iDeCoと新NISAでは投資対象商品に違いがあり、新NISAの選択肢が幅広いことが特徴です。それでは、それぞれ詳しくみていきましょう。
iDeCoの投資対象商品
iDeCoの大きな特徴は、投資信託だけではなく、定期預金等の元本確保型の商品も選べることです。
リスクがある商品での運用は避けたいけれど、iDeCo制度の活用で何らかのメリットを受けたいという人は、iDeCoで元本保証商品を選びましょう。
掛金の所得控除で税金を安くでき、なおかつ資産の元本が保障されます。
ただし、元本保障の商品を選ぶと、運用益はほぼゼロのため「運用益が非課税になる」というメリットを活かすことはできません。
実際のiDeCo(個人型)の運用商品選択状況では、以下のような割合になっており、運用益を期待できる「投資信託」を選ぶ人が最も多いことがわかります。
| 運用商品 | 2023.3末の割合 |
| 預貯金 | 25.6% |
| 保険 | 8.6% |
| 投資信託・金銭信託等 | 64.5% |
| 処理待機資金等 | 1.3% |
出典:確定拠出年金統計資料(運営管理機関連絡協議会)
iDeCoや新NISAの目的は、将来の物価上昇で資産が目減りしないように「増やしながら貯める」ことが目的です。
元本保証の商品を選ぶと、元本割れのリスクがないかわりに資産が増えることもないため、将来の資産価値が下がる可能性が高くなります。
また、iDeCoにおける運用商品は、金融機関によって違うものの、新NISAに比べるとかなり少ないというデメリットがあります。
例えば、みずほ銀行のiDeCoのラインナップは、定期預金が1本、投資信託が約20本ほどです。さまざまな運用商品から選びたいという人は、運用商品の選択肢が多い新NISAがおすすめです。
新NISAの投資対象商品
新NISAでは、定期預金などの元本保証の商品はないものの、投資商品の選択肢が多いのが魅力です。
新NISAの積み立て枠対象の投資商品は金融庁が定めており、以下のように多くの商品を選べます。
| 国内 | 内外 | 海外 | ||
| 公募投信 | 株式型 | 51本 | 27本 | 76本 |
| 資産複合型 | 5本 | 119本 | 2本 | |
| ETF | 3本 | ー | 5本 | |
また、新NISAの成長投資枠では、すべての上場株式と投資信託(除外あり)・ETFなどに投資ができます。また、投資信託・ETFはどの証券会社も1,000本前後の選択肢があります。
選択肢が多いと選びにくいと感じる場合もありますが、自分の考えに合った商品を自由に選べることが新NISAのメリットといえるでしょう。
50代以降の転職でお困りの方はBEYOND AGEまでご相談ください
iDeCoのメリット・デメリット

iDeCoには、今まで説明してきたように、以下のようなメリットとデメリットがあります。
| iDeCoのメリット | iDeCoのデメリット |
| 運用益が非課税になる | 資金の引き出しは最短で60歳 |
| 毎月の掛金が全額所得控除の対象となり、税金が軽減される | 運用商品の選択肢が限られている |
| 将来の受取時にも税金が優遇される | 口座を維持するために加入者手数料(国民年金基金連合会に払う手数料)が必ずかかる(金融機関に支払う「運営管理手数料」は無料の金融機関もある) |
| 定期預金など元本保証商品が選べる |
iDeCoの最大のメリットは「所得控除」であり、所得が大きければ大きいほど、得られる節税メリットは大きくなります。
また、後述しますが、iDeCoを一時金として受け取る際には「退職所得控除」を適用でき、
出金時にも税金がかかりにくくなっています。
そのかわりに、資産の引き出し時期に制限があったり、選べる投資商品が限られているというデメリットもあります。
「所得控除における節税メリット」と「投資対象商品が少なく、自由に引き出せない」
というデメリットを比較して、iDeCoにするかどうかを判断するようにしましょう。
50代以降の転職でお困りの方はBEYOND AGEまでご相談ください
新NISAのメリット・デメリット

新NISAのメリットデメリットは以下のようになっており、非課税枠が合計1,800万円と大きく、さまざまな投資商品を選べることが大きな魅力です。
| 新NISAのメリット | 新NISAのデメリット |
| 運用益が非課税になる | 損失が出ても他の運用口座の利益を損益通算できない |
| いつでも引き出せる | 所得控除がない |
| 株式や投資信託、ETFに投資できる | |
| 運用期間の制限がない |
非課税枠は「投資元本の1,800万円まで」となっているため、例えば資産が倍の3,600万円に増えた場合でも、利益に税金がかからずすべて手元に残ります。
それに対して、iDeCoは運用益が非課税になるものの、iDeCo一時金として出金する際に「退職所得控除」枠を超えた分に対しては、税金がかかります。
このように、iDeCoでは一時金で出金する際に、全額を非課税で受け取れないケースも出てきますが、新NISAでは投資原本1,800万円までは課税がなく、すべての利益を受け取れることが大きなメリットといえます。
新NISAには所得控除がないというデメリットはありますが。それ以外の点はiDeCoより新NISAのほうが自由度が高く、利用しやすい制度といえるでしょう。
50代以降の転職でお困りの方はBEYOND AGEまでご相談ください
55歳からiDeCo・新NISAで10年間積立投資した場合の運用シミュレーション

iDeCoと新NISAで毎月一定額を10年間積み立てて運用した場合、どれくらいのお金を貯められるのでしょうか。3つのパターンで検証してみましょう。
毎月1万円をiDeCo・新NISAで積立投資した場合
毎月1万円を年利3%で10年間積み立てることを想定した場合、損益のシミュレーションは以下のようになります。
| 10年間の積立額 | 運用益(10年間) | 所得控除における税金軽減額(10年間) | 運用益+所得控除による税金軽減額(10年間) | 元本と運用益・税金軽減額の合計 | |
| 新NISA | 1,200,000円 | 197,919円 | 0円 | 197,919円 | 1,397,919円 |
| iDeCo(課税所得300万円) | 1,200,000円 | 197,919円 | 240,000円 | 437,919円 | 1,637,919円 |
| iDeCo(課税所得500万円) | 1,200,000円 | 197,919円 | 360,000円 | 557,919円 | 2,117,919円 |
iDeCoで運用した資金を一時金で引き出す際に、すべて非課税で受け取れるかは、受取時の退職所得控除額によります。
新NISAは投資元本が1,800万円以内なので、すべて非課税で受け取れます。
毎月2万円をiDeCo・新NISAで積立投資した場合
毎月1万円を年利3%で10年間積み立てることを想定した場合、損益のシミュレーションは、以下となっています。
| 10年間の積立額 | 運用益(10年間) | 所得控除における税金軽減効果(10年間) | 運用益+所得控除による税金軽減額(10年間) | 元本と運用益・税金軽減額の合計額 | |
| 新NISA | 2,400,000円 | 395,838円 | 0円 | 397,838円 | 1,397,919円 |
| iDeCo(課税所得300万円) | 2,400,000円 | 395,838円 | 480,000円 | 875,838円 | 3,275,838円 |
| iDeCo(課税所得500万円) | 2,400,000円 | 395,838円 | 720,000円 | 1,115,838円 | 3,515,838円 |
どちらもすべて非課税で受け取れるかは、受取時の退職所得控除額によります。
毎月8万円をiDeCo・新NISAで積立投資した場合
個人事業主はiDeCoの上限額が月6.8万円です。
個人事業主の人が毎月6.8万円をiDeCo・新NISAで運用すると想定し、シミュレーションすると以下のようになります。
| 10年間の積立額 | 運用益(10年間) | 所得控除における税金軽減効果(10年間) | 運用益+所得控除における税金軽減額(10年間) | 元本と運用益・税金軽減額の合計額 | |
| 新NISA | 8,160,000円 | 1,345,850円 | 0円 | 1,345,850円 | 9,505,850円 |
| iDeCo(課税所得300万円) | 8,160,000円 | 1,345,850円 | 1,632,000円 | 2,977,850円 | 11,137,850円円 |
| iDeCo(課税所得500万円) | 8,160,000円 | 1,345,850円 | 2,448,000円 | 3,793,850円 | 11,953,850円 |
このように、個人事業主は月額拠出金の上限が大きいため、所得控除で大きな恩恵を受けることができます。
ただし、貯まる額も大きいため、退職所得控除額を超え、iDeCo一時金を受け取る際には、税金が発生する可能性が高いことを覚えておきましょう。
50代以降の転職でお困りの方はBEYOND AGEまでご相談ください
まとめ
iDeCoと新NISAを55歳から始める場合は、自分に合った方法を選ぶことが大切です。ある程度の収入がある人や、個人事業主の人は所得控除があるiDeCoのメリットが大きくなります。資金を自由に引き出したい人や、株や投資信託などさまざまな商品で運用したい人はNISAがおすすめです。
iDeCoとNISAのメリットデメリットをよく理解して、無理のない金額で運用を始めるようにしましょう。
※本記事は2024年6月の情報を元に作成されており、今後新NISAやiDeCoの制度内容が変わる可能性があります。