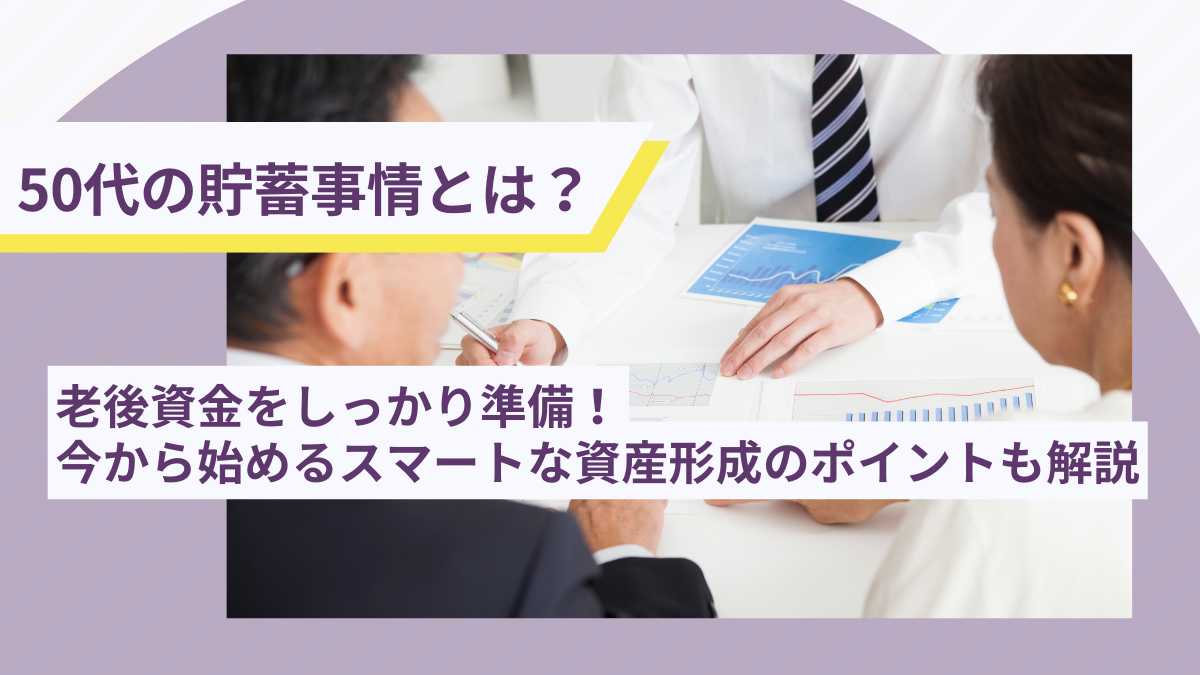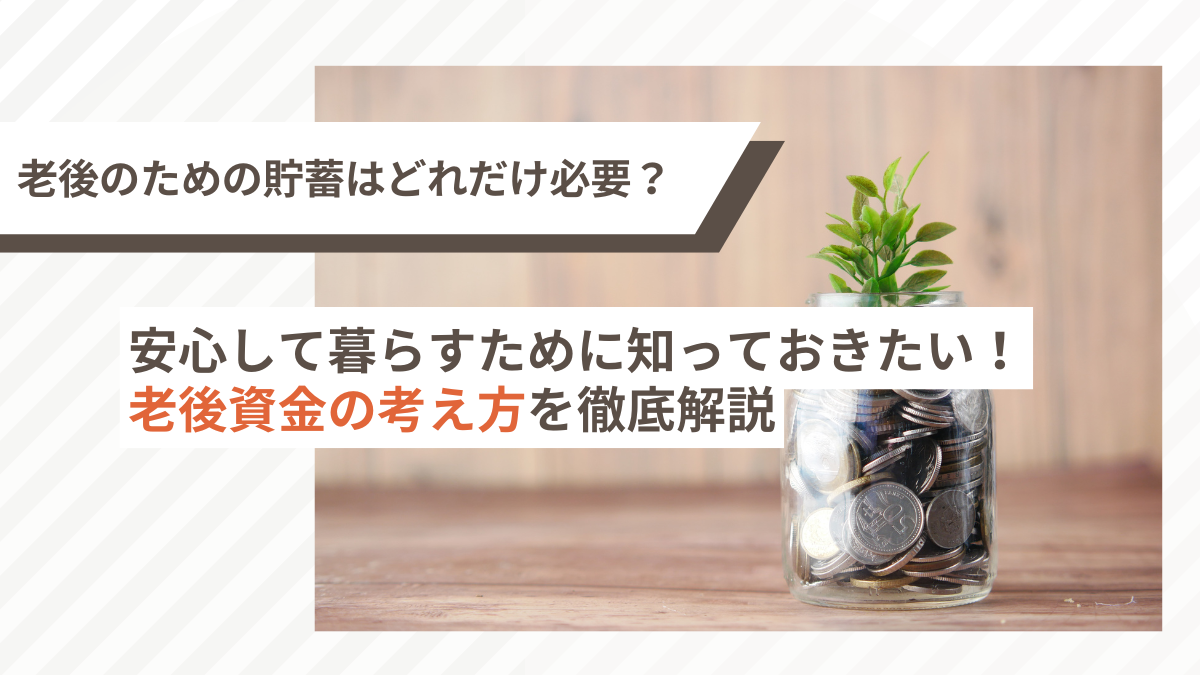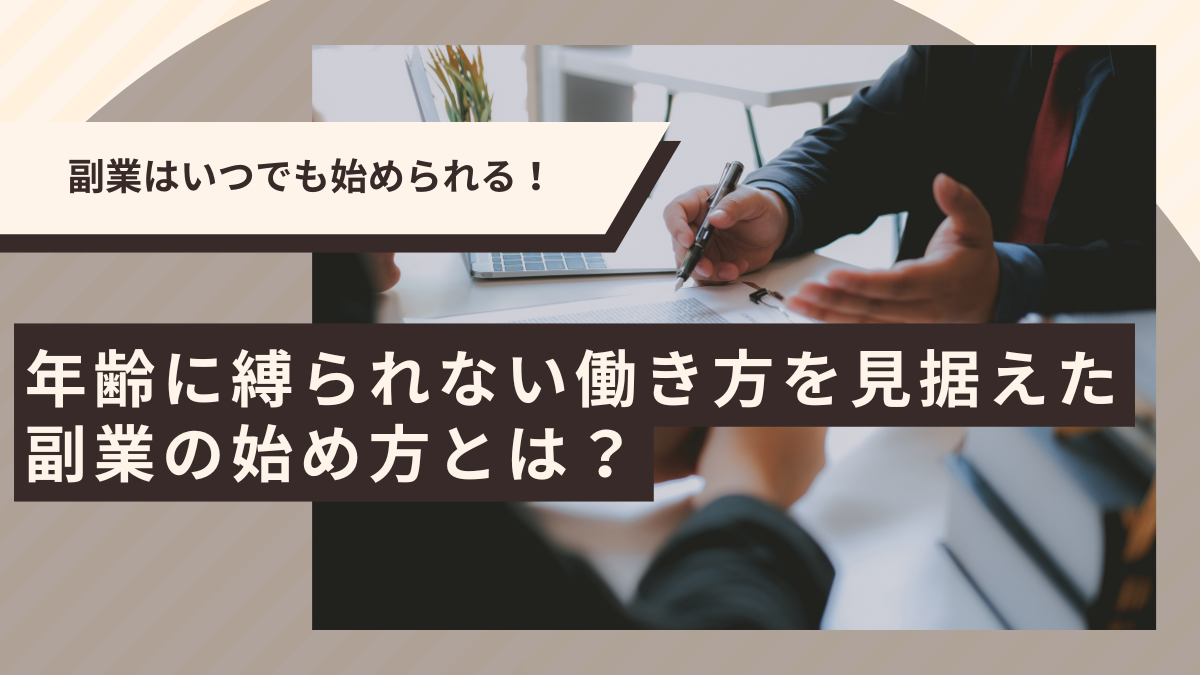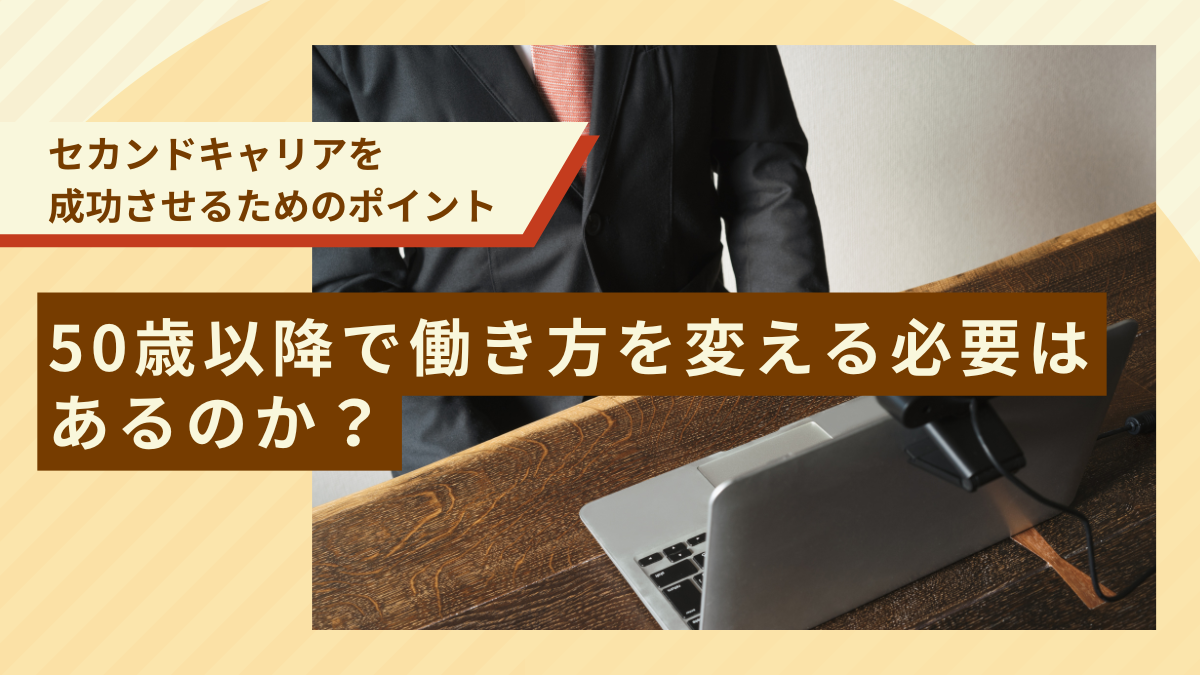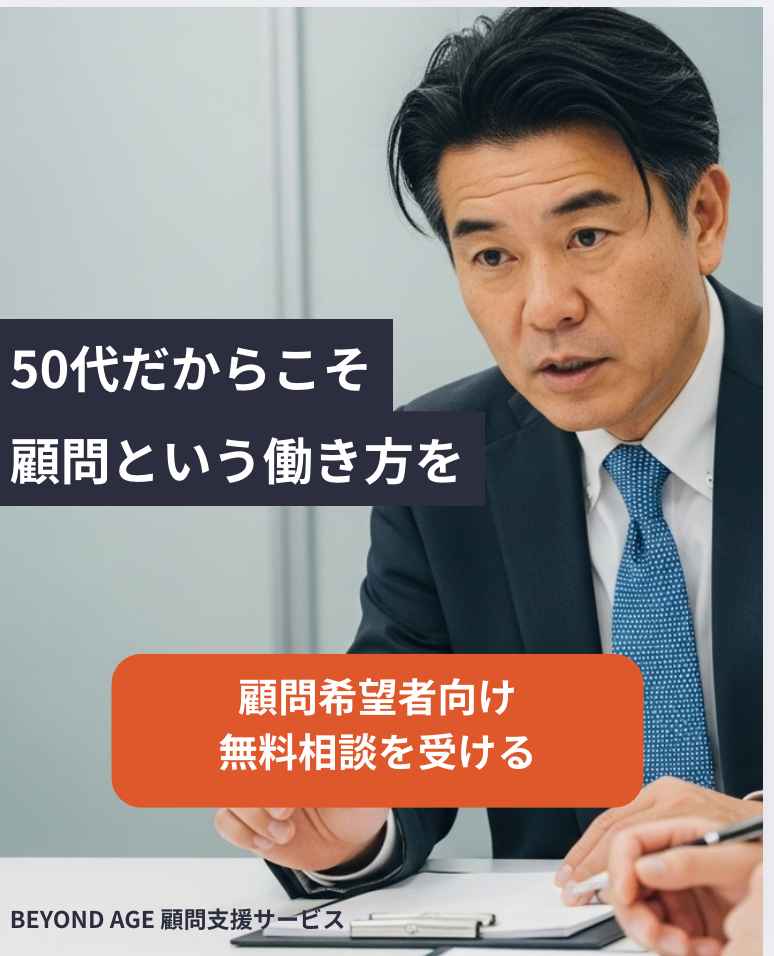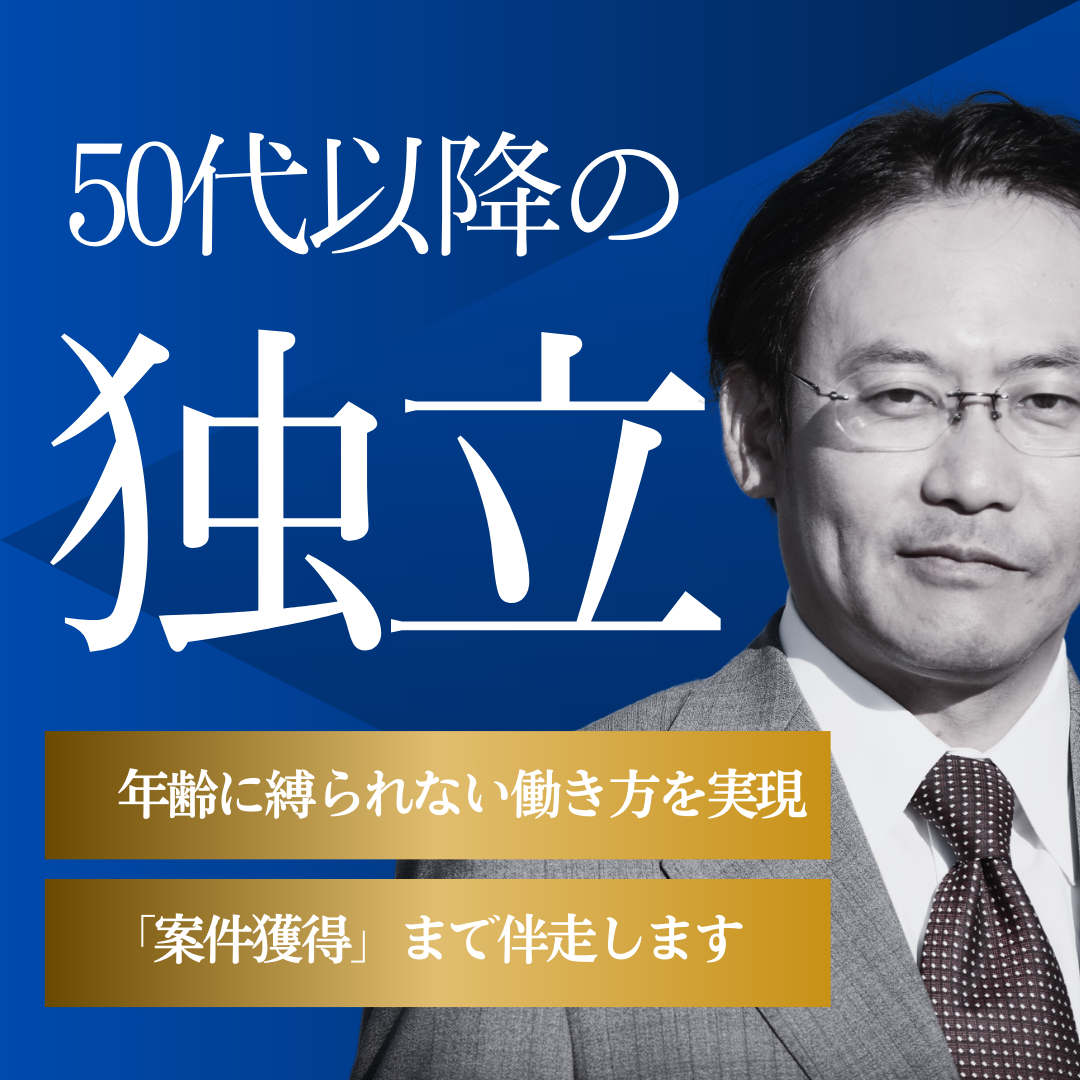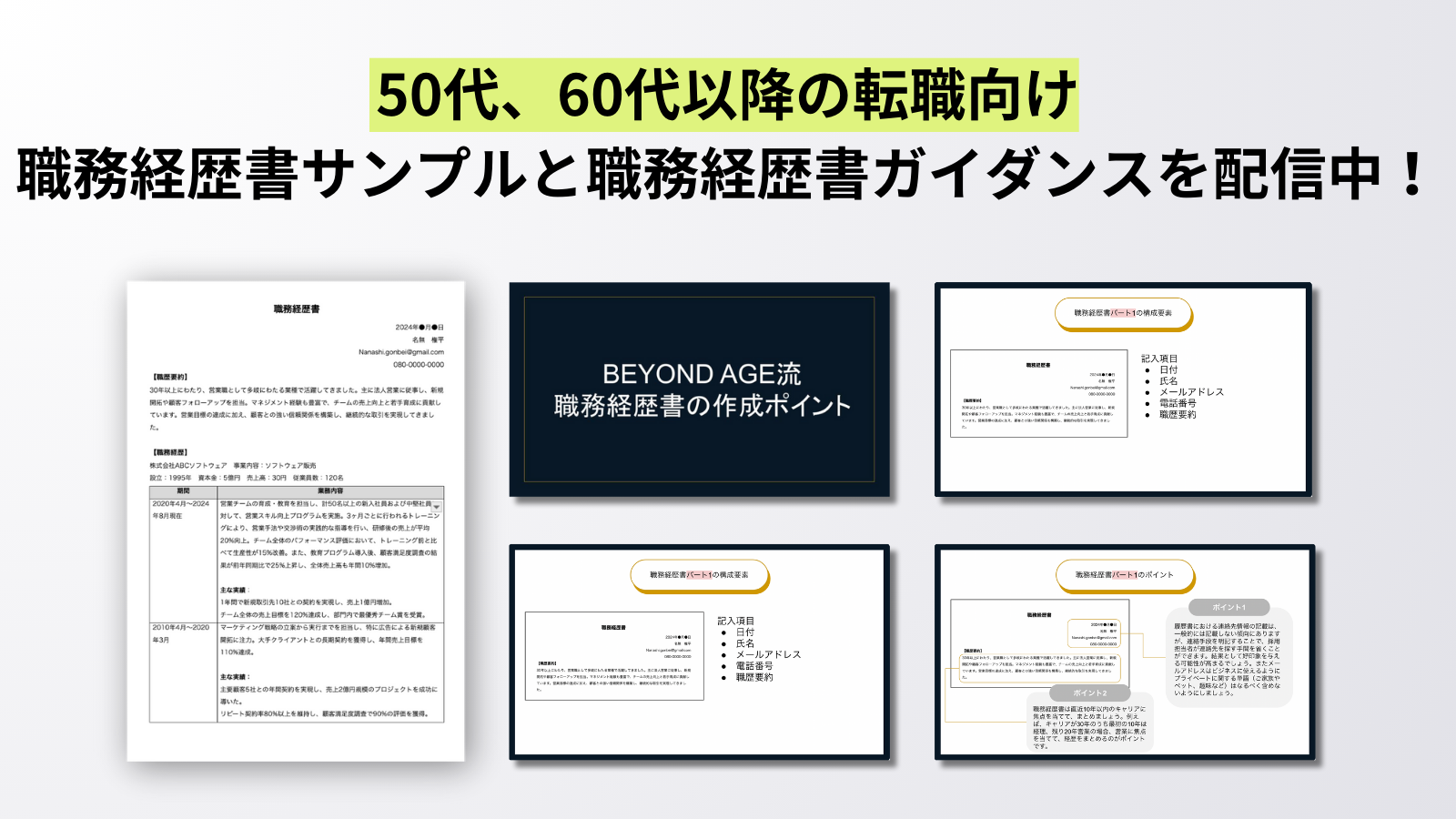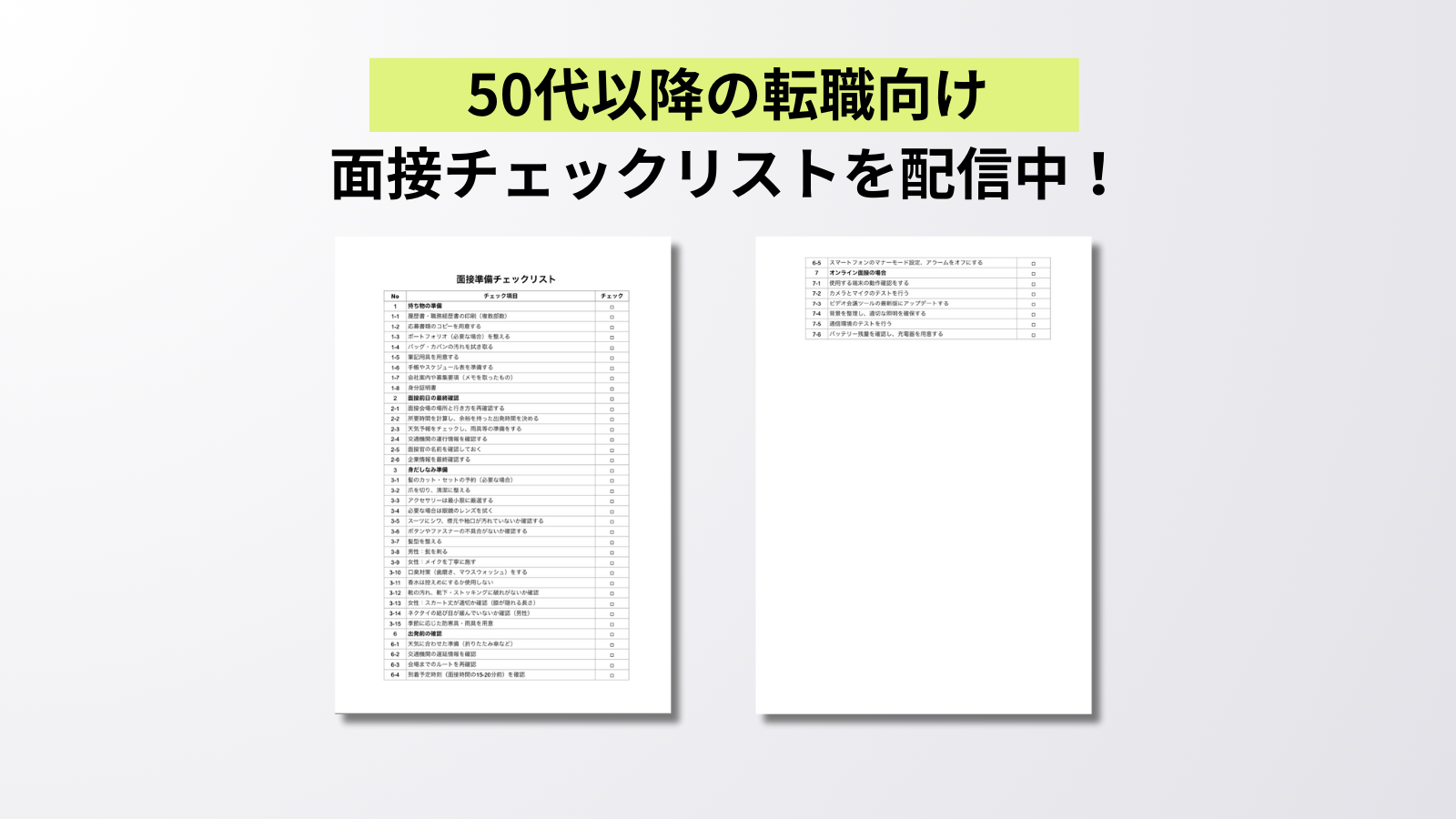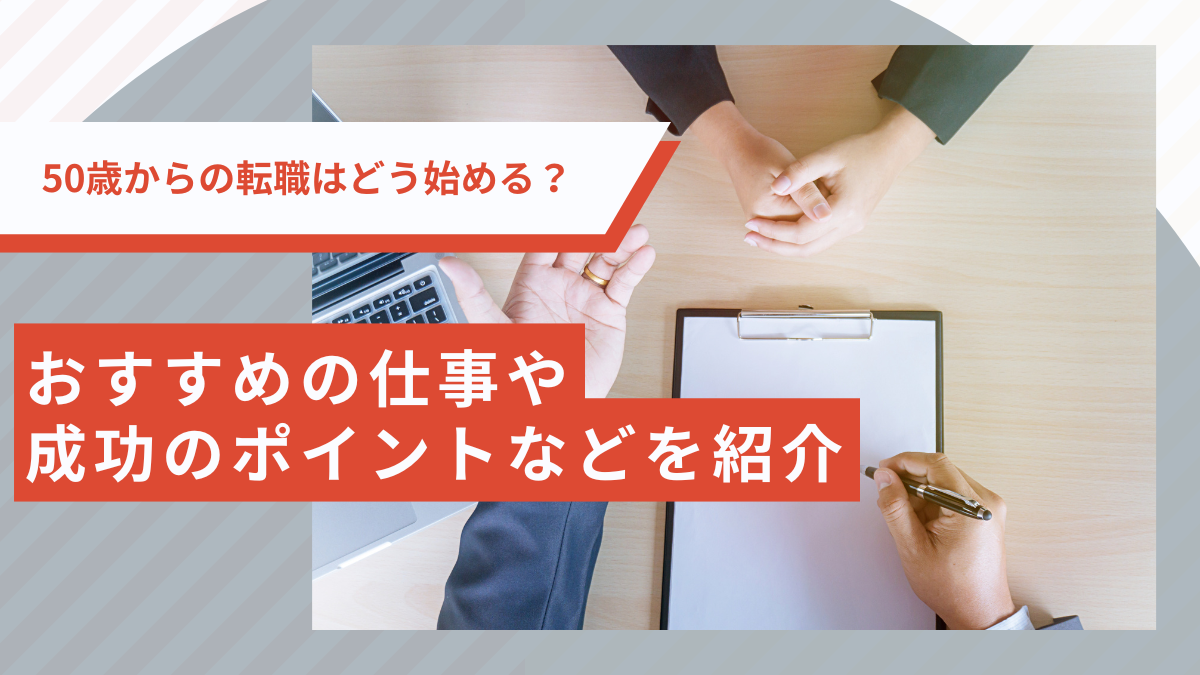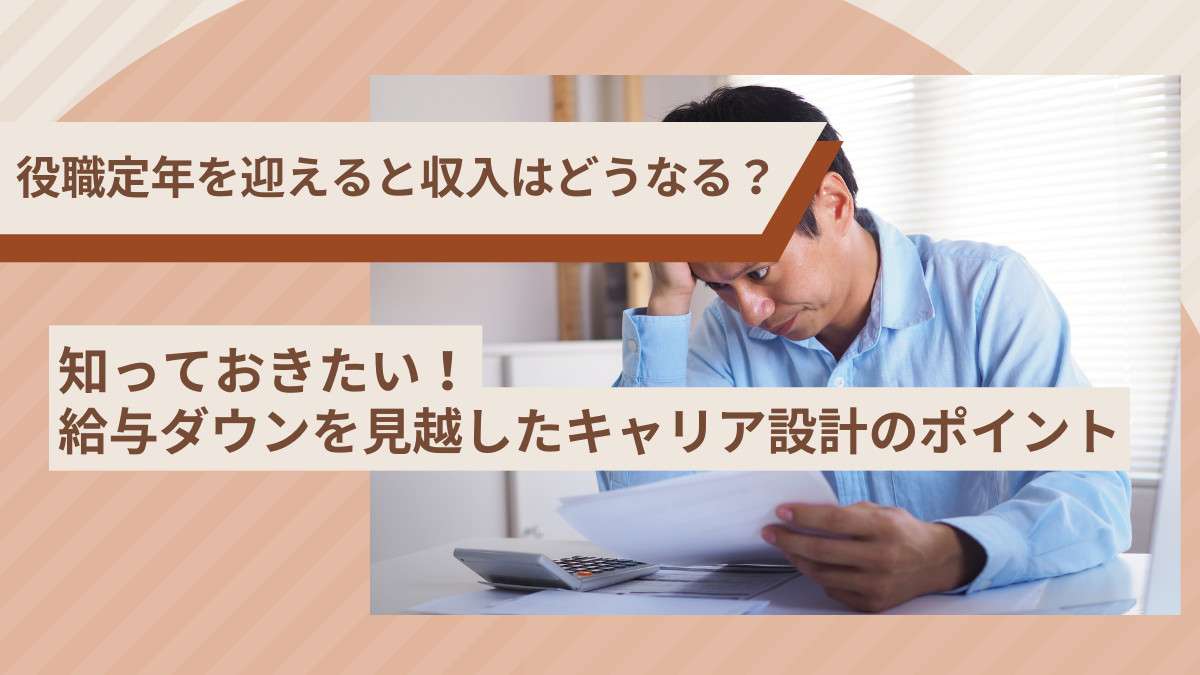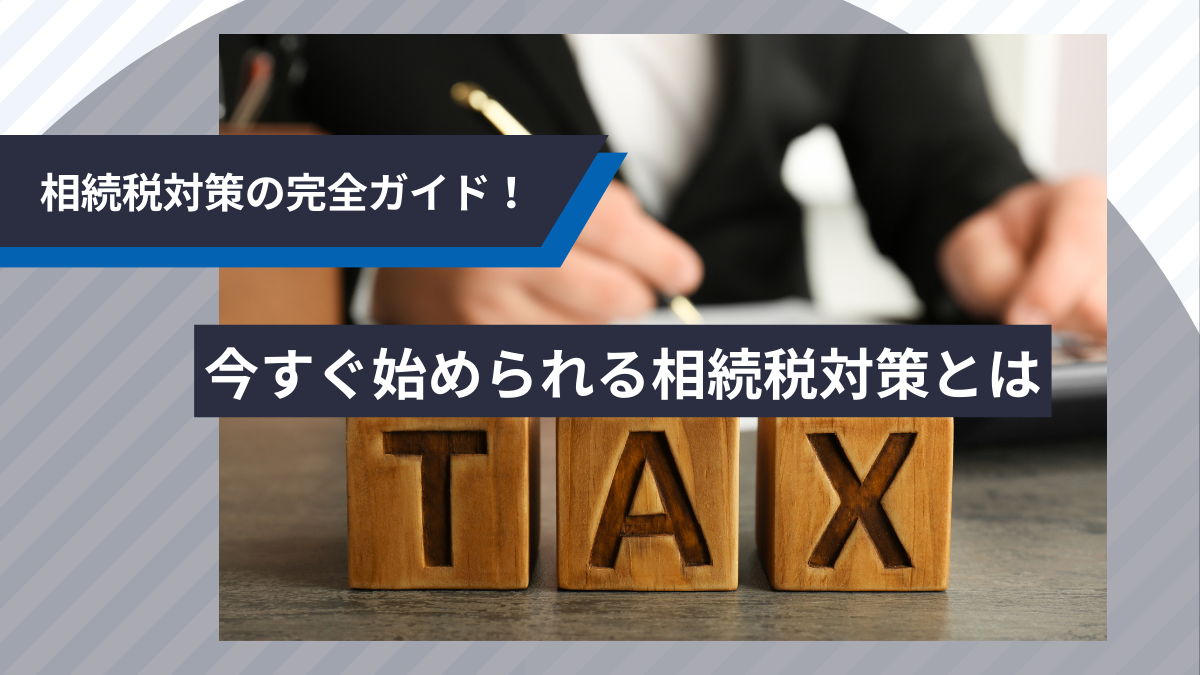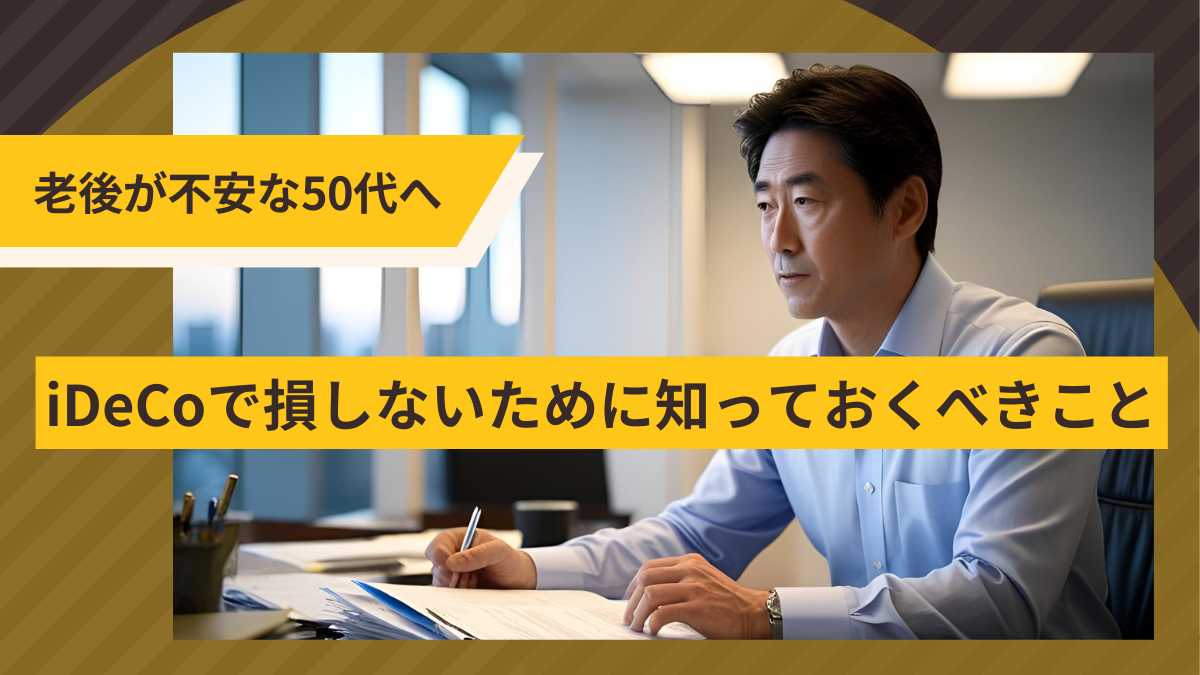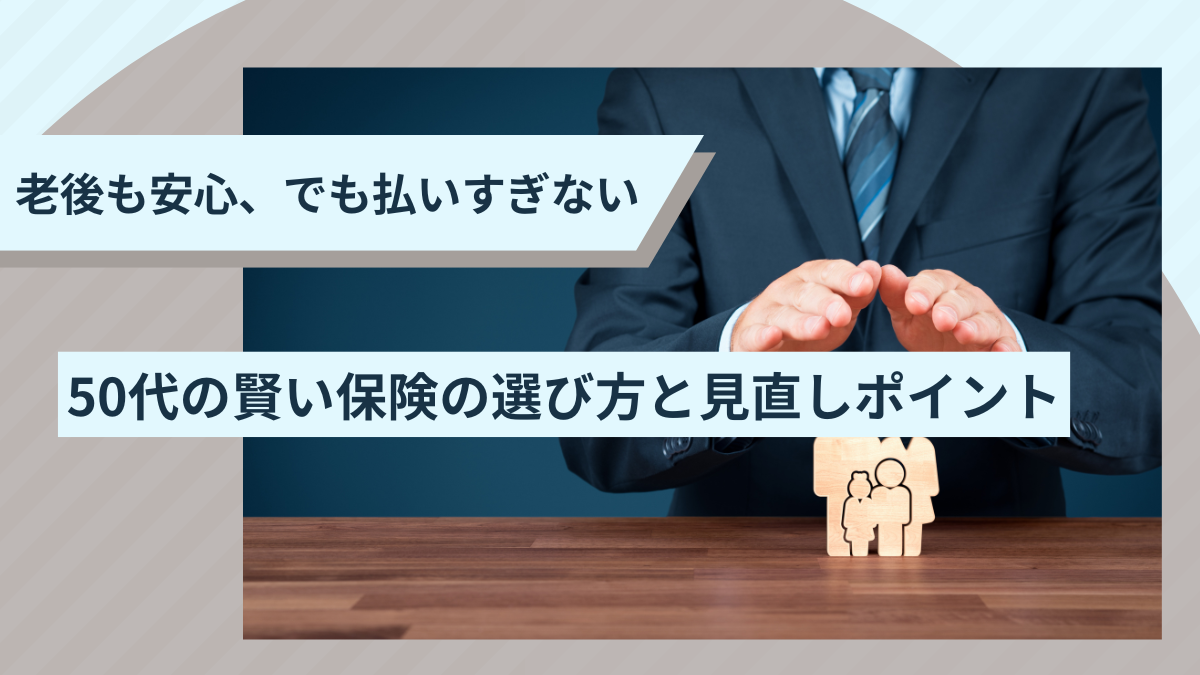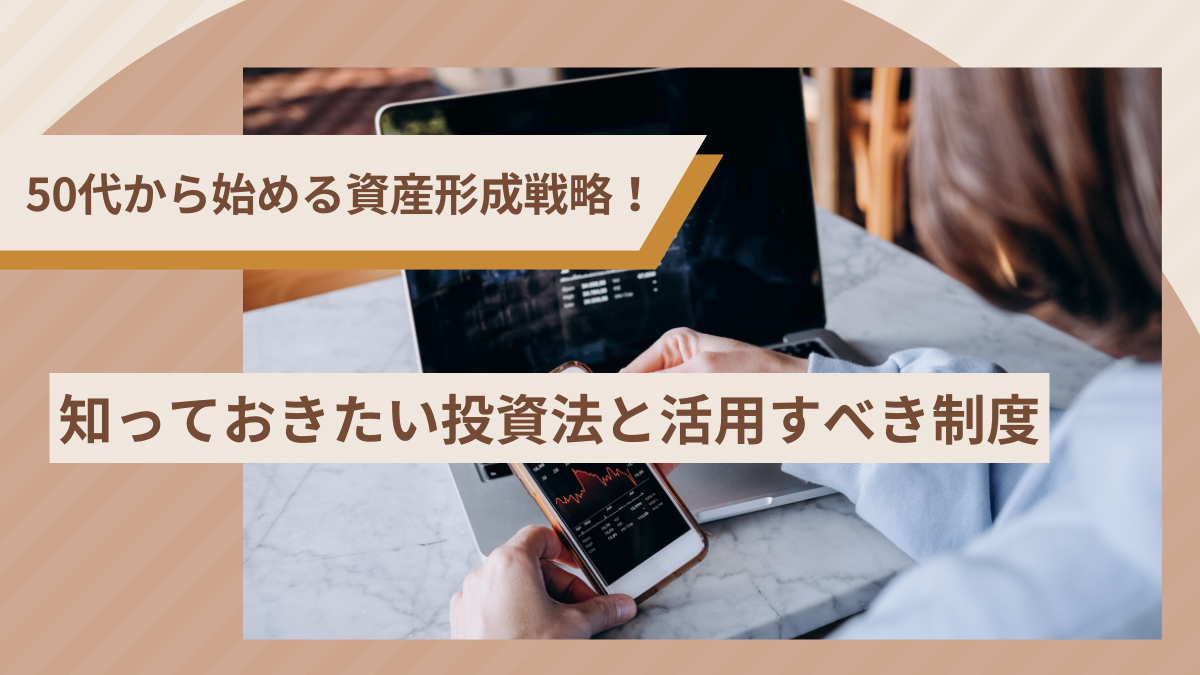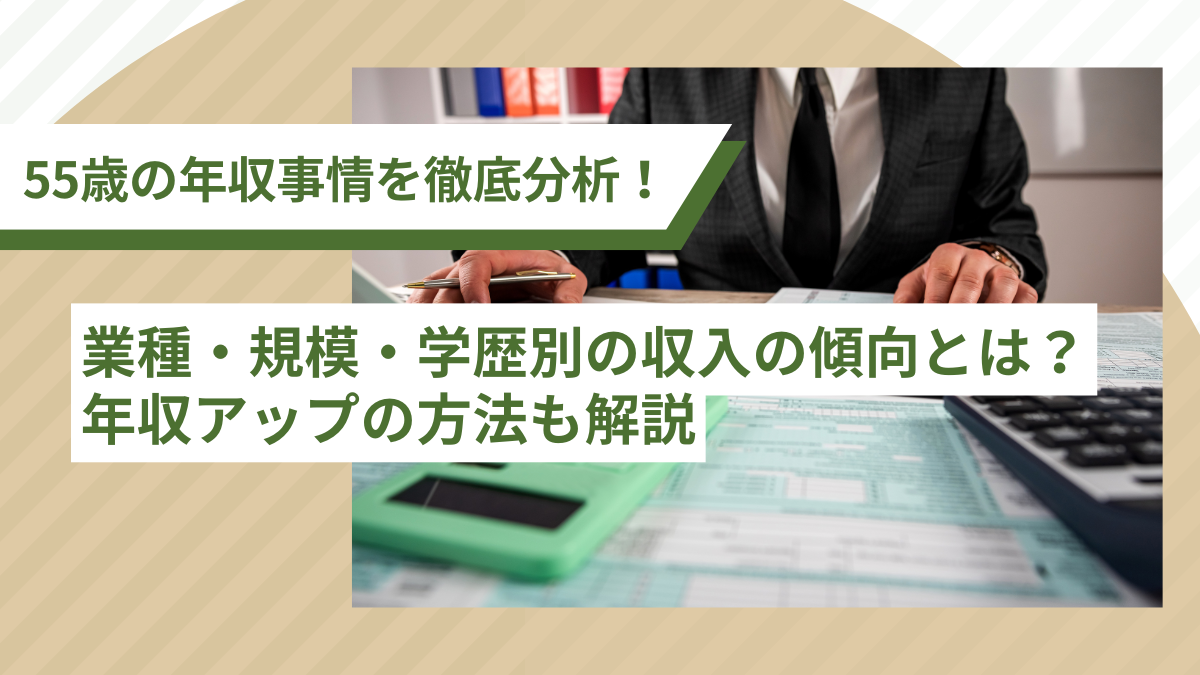50歳代は老後について少しずつ考え始める時期ですが、平均貯蓄額や中央値はどれくらいなのでしょうか。老後資金として、どれくらいの金額を目標に、50歳代から貯蓄すれば良いのでしょうか。
この記事では、金融広報中央委員会が実施した「家計の金融行動に関する世論調査 (令和5年・二人以上世帯調査)」のデータを基に、さまざまな角度から解説します。
50歳代の方の貯蓄額や保有している金融資産の種類、手取り収入における貯蓄割合など、参考になる情報をお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。

伊藤FP事務所代表。ファイナンシャルプランナー(AFP)兼ライター。大学卒業後、証券会社・保険コンサルタントを経て事務所代表兼フリーライターとして活動を始める。家計の見直しから税金・保険・資産運用まで、人生の役に立つ記事を幅広く執筆。
50代以降の転職でお困りの方はBEYOND AGEまでご相談ください
50歳代の平均貯蓄額はどれくらい?

50歳代の平均貯蓄額(金融資産を保有している世帯が対象)は、平均で1,611万円、中央値で745万円です。
割合が最も多いのは、「貯蓄額が3,000万円以上」で、15.5%です。
次に多いのは、「100万円未満」で12.5%、「1,000万円〜1,500万円未満」が12.2%で、ほぼ同じ割合になっています。
| 金融資産額 | 割合 |
| 100万円未満 | 12.5% |
| 100~200万円未満 | 8.9% |
| 200~300万円未満 | 5.2% |
| 300~400万円未満 | 5.4% |
| 400~500万円未満 | 5.2% |
| 500~700万円未満 | 7.7% |
| 700~1,000万円未満 | 7.5% |
| 1,000~1,500万円未満 | 12.2% |
| 1,500~2,000万円未満 | 5.8% |
| 2,000~3,000万円未満 | 7.4% |
| 3,000万円以上 | 15.5% |
3,000万円以上の人が多いのは、資産を着実に増やしてきた人に加えて、早期退職や転職などで、退職金を50代で受け取った人も一定数いるためと考えられます。
老後に自分達で貯めなければならない金融資産は2,000万円と言われていますが、中央値を見ると、今後しっかりと貯蓄しなければならない人が多いことがわかります。
老後2,000万円問題が話題になって以降、「老後のためにお金を貯めておかなければならない」ということが、幅広い年代で浸透してきました。 「老後に安心して暮らせるだけの貯蓄を貯めたい」と考える人も多いと思いますが、実際に2,000万円[…]
年代別の平均貯蓄額の平均値と中央値
年代別の平均貯蓄額の平均・中央値は以下のようになっており、多くの人がコツコツと着実に貯蓄を増やしていることがわかります。
| 年代 | 平均 | 中央値 |
| 20歳代 | 403万円 | 171万円 |
| 30歳代 | 856万円 | 337万円 |
| 40歳代 | 1,236万円 | 500万円 |
| 50歳代 | 1,611万円 | 745万円 |
| 60歳代 | 2,588万円 | 1,200万円 |
| 70歳代 | 2,188万円 | 1,100万円 |
単純に計算すると、50歳代から60歳代の10年間で、中央値では455万円増えていることから、毎月約38,000円積み立てて増やした計算です。
40歳代から50歳代にかけては、10年間で中央値は545万円増えていることから、毎月約20,000円積み立てた計算になります。
このことから、50歳代から60歳代にかけては、収入が多い世代であり、なおかつ子育ても一段落して教育費の支出も減るため、余剰資金をしっかりと貯蓄にまわしている人も多いと考えられます。
また、60歳代の金融資産額は急に増えて、平均値2,588万円、中央値は1,200万円です。一般的には60歳代で退職金を受け取るケースが多いため、退職金により、貯蓄額が増えたと考えられます。
50代は今後のキャリアだけでなく、老後資金についても悩み始める時期です。特に、これまで十分な貯蓄ができなかった人は、さまざまな要素を考慮してキャリアを決める必要があります。 今回は、4回の転職を経験し、現在は人事部門で従業員のモチベ[…]
50代以降の転職でお困りの方はBEYOND AGEまでご相談ください
50歳代は貯蓄額が多いが借入金もあるケースが多い

50歳代は、一定の貯蓄額がある一方で、住宅ローンなどの借入金もあり、毎月返済しているケースも多いと考えられます。
50歳代の借入金の平均は、1,077万円、中央値は800万円です。
借入金残高の詳細は、以下のようになっています。
| 借入金残高 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 |
| 50万円未満 | 9.8% | 7.6% | 12.7% |
| 50~100万円未満 | 7.8% | 11.1% | 16.5% |
| 100~200万円未満 | 8.6% | 11.8% | 20.3% |
| 200~300万円未満 | 4.1% | 9.0% | 16.5% |
| 300~500万円未満 | 5.7% | 15.3% | 3.8% |
| 500~700万円未満 | 7.8% | 7.6% | 7.6% |
| 700~1,000万円未満 | 9.0% | 6.9% | 1.3% |
| 1,000~1,500万円未満 | 13.5% | 9.0% | 8.9% |
| 1,500~2,000万円未満 | 11.0% | 2.8% | 2.5% |
| 2,000万円以上 | 20.0% | 11.0% | 7.6% |
50歳代は、1,000万円以上借入をしている世帯が、44.5%にのぼっています。このことから、貯蓄をしつつ住宅ローン返済も同時にしている世帯が多いと考えられます。
60歳代、70歳代では高額な借入をしている人の割合が減っているので、退職金を使って返済を行う人が一定数いると考えられます。
50歳代では住宅ローンを返済しつつ、老後資金を貯蓄していく必要があるため、計画的な貯蓄・返済計画を立てることが大切だといえるでしょう。
50代以降の転職でお困りの方はBEYOND AGEまでご相談ください
50歳代が保有している金融資産の種類と割合は?

50歳代の「現在保有している金融資産は何ですか?」という質問の回答(複数回答)は、以下のとおりです。
| 保有している金融商品 | 割合 |
| 預貯金 | 96.6% |
| 積立型保険商品 | 35.3% |
| 株式 | 30.6% |
| 個人年金保険 | 27.2% |
| 投資信託 | 25.7% |
| 財形貯蓄 | 14.5% |
| 債券 | 6.4% |
| 金銭信託 | 4.9% |
| その他金融商品 | 6.3% |
| いずれも保有していない | 2.8% |
預貯金はほとんどの人が保有しており、次に多いのは積立型の保険商品です。株式も約30%の人が保有しており、リスクを伴う金融商品で運用する人も一定数いることがわかります。
「株式」と「投資信託」を保有している人の割合は、年代別にみると以下のようになっています。
| 年代 | 株式 | 投資信託 |
| 20歳代 | 18.1% | 27.5% |
| 30歳代 | 26.9% | 29.0% |
| 40歳代 | 29.5% | 30.3% |
| 50歳代 | 30.6% | 25.7% |
| 60歳代 | 36.3% | 28.4% |
| 70歳代 | 39.1% | 26.8% |
年代が上がるにつれて、株式と投資信託を保有している人の割合が増加しているという興味深い結果が得られています。
年齢が上がるにつれ、投資についての知識や経験が深まることから、割合が増えると考えられます。また、70代の割合も増加しており、退職金を一部株式や投資信託で運用する人も多いと考えられます。
50歳代が貯蓄するときの金融商品の選び方
50歳代では多くの人が、複数の金融商品を組み合わせながら貯蓄をしていることがわかりました。
50歳代の人が、金融商品を選ぶ際に基準にしていることは「収益性」「安全性」「流動性」「商品が理解しやすいこと」の4点で、それぞれの細かい判断基準とその割合は以下のようになっています。
| 金融商品の選択基準 | 割合 | |
| 収益性 | 利回りが良いから | 20.2% |
| 将来の値上がりが期待できる | 15.1% | |
| 安全性 | 元本が保証されているから | 23.0% |
| 取扱金融機関を信用しているから | 5.9% | |
| 流動性 | 現金に換えやすい | 7.1% |
| 少額でも預入・引出が自由にできる | 12.8% | |
| 商品内容が理解しやすいから | ー | 4.4% |
| その他 | 11.4% |
「元本が保証されているから」が23.0%と最も多くなっていますが、利回りや将来の値上がりを期待して運用する人の割合も20%前後となっています。
元本を守るだけでなく、運用益を期待する人が多いこともわかります。50歳代は、60歳もしくは65歳の定年まで、約10年~15年あります。元本保証の商品で貯蓄するか、ある程度運用益を期待した商品選びをするのかを、よく検討して決めるようにしましょう。
50歳代が目標にする貯蓄額はどれくらい?
50歳代は老後にむけて貯蓄を増やしたい時期ですが、どれくらいの金額を目標とすれば良いのでしょうか。
「知るぽると」の調査結果によると、50歳代が目標にする金融資産残高は、以下のようになっています。
| 金融資産額 | 割合 |
| 200万円未満 | 10.4% |
| 200~300万円未満 | 2.3% |
| 300~500万円未満 | 2.8% |
| 500~700万円未満 | 9.0% |
| 700~1,000万円未満 | 0.3% |
| 1,000~1,500万円未満 | 15.4% |
| 1,500~2,000万円未満 | 2.2% |
| 2,000~3,000万円未満 | 14.5% |
| 3,000~5,000万円未満 | 9.7% |
| 5,000~7,000万円未満 | 8.1% |
| 7,000万円以上 | 9.4% |
目標額が「1,000万円〜1,500万円未満」と「2,000万円〜3,000万円未満」がどちらも約15%前後で、最も高い割合になっています。
また、50歳代の「目標とする金融資産残高」は、平均で3,099万円、中央値で1,500万円です。
実際の50歳代の平均貯蓄額は最初に紹介したように「平均で1,611万円」「中央値で745万円」です。このように、理想と現実には大きな開きがあることがわかります。
目標額に少しでも近づくための方法として、以下の3つが考えられます。
- 節約して貯蓄にまわすお金を増やす
- 副業や個人事業主としての独立など、収入を増やす働き方を考える
- 株や投資信託など、値上がりが期待できる金融商品を選ぶ
預金だけではお金は増えません。「貯めつつ増やす」を実現するためには、リスク資産を組み込んだ運用が重要といえます。
50代以降の転職でお困りの方はBEYOND AGEまでご相談ください
50歳代の年間手取り収入からの貯蓄割合

50歳代では、収入のどれくらいの割合を貯蓄に充てているのでしょうか。「知るぽると」の調査によると、50歳代では収入の12%を貯蓄に充てられており、細かい内訳は以下のようになっています。
| 手取り収入からの貯蓄割合 | 割合 |
| 5%未満 | 6.9% |
| 5~10%未満 | 15.7% |
| 10~15%未満 | 20.2% |
| 15~20%未満 | 5.2% |
| 20~25%未満 | 8.3% |
| 25~30%未満 | 1.7% |
| 30~35%未満 | 5.7% |
| 35%以上 | 8.1% |
| 貯蓄しなかった | 28.1% |
貯蓄できなかったという割合も約28%おり、お金を貯める余裕がない世帯も一定数いることがわかります。貯蓄ができない場合は、支出を削減したり、逆に副業などで収入を増やすなどして、老後資金のため、少しでも貯蓄することが大切です。
50代以降の転職でお困りの方はBEYOND AGEまでご相談ください
老後の生活に必要な資金はどれくらい?

50歳代で貯蓄したお金は老後の生活の大きな支えになりますが、老後の生活に必要な資金はどれくらいなのでしょうか。
「総務省統計局の家計調査(2023年)」の統計をもとに、「二人以上世帯」と「単身世帯」にわけて解説します。
二人以上世帯
65歳以上の、二人以上世帯の生活費の内訳は、以下のとおりです。
| 実収入 | 24万4,580円 |
| 消費支出 | 25万959円 |
| (食費) | 7万2,930円 |
| (住居) | 1万6,827円 |
| (光熱・水道) | 2万2,422円 |
| (家具・家事用品) | 1万477円 |
| (被服及び履物) | 5,159円 |
| (保健医療) | 1万6,879円 |
| (交通・通信) | 3万729円 |
| (教育娯楽) | 2万4,690円 |
| (その他の消費支出) | 5万839円 |
| 非消費支出 | 3万1,538円 |
| (社会保険料) | 1万8,435円 |
| (直接税) | 1万3,090円 |
「消費支出」と「非消費支出」の合計は1ヶ月あたり28万2,497円となっています。年金等の実収入は24万4,580円のため、毎月37,917円の赤字になります。
二人とも同年齢で、85歳まで生きると仮定して計算してみましょう。
65歳~85歳までの20年間、毎月赤字の状態が続くと仮定すると
37,917円×12ヶ月×25年=1,137万5,100円
となり、約1,137万円を貯蓄で用意しなければならない計算になります。50歳から老後に向けての貯蓄目標額は、まずはこの金額を目標にしましょう。
ただし、この金額は生活していく最低限の生活費です。ゆとりがある老後を送りたい場合は、より多くの老後資金を用意する必要があります。
単身世帯
「知るぽると」の調査は二人以上世帯ですが、ここでは65歳以上の単身世帯の生活費をみてみましょう。
生活費の内訳は、以下のとおりです。
| 実収入 | 12万6,905円 |
| 消費支出 | 14万5,430円 |
| (食費) | 4万103円 |
| (住居) | 1万2,564円 |
| (光熱・水道) | 1万4,436円 |
| (家具・家事用品) | 5,923円 |
| (被服及び履物) | 3,241円 |
| (保健医療) | 7,981円 |
| (交通・通信) | 1万5,086円 |
| (教育娯楽) | 1万5,277円 |
| (その他の消費支出) | 3万821円 |
| 非消費支出 | 1万2,356円 |
| (社会保険料) | 5,799円 |
| (直接税) | 6,437円 |
「消費支出」と「非消費支出」の合計額が15万7,786円、年金等の実収入が12万6,905円のため、毎月30,881円の赤字です。
平均寿命は男性81歳・女性87歳のため、年金受給開始から平均寿命までの年数は、男性が約16年・女性が約22年と計算できます。
よって、年金以外に必要な貯蓄額は
【男性】30,881円×12ヶ月×16年=592万9,152円
【女性】30,881円×12ヶ月×22年=815万2,584円
と計算できます。この金額を、貯蓄の最初の目標として、計画的に貯蓄をするようにしましょう。
老後2,000万円問題が話題になって以降、「老後のためにお金を貯めておかなければならない」ということが、幅広い年代で浸透してきました。 「老後に安心して暮らせるだけの貯蓄を貯めたい」と考える人も多いと思いますが、実際に2,000万円[…]
50代以降の転職でお困りの方はBEYOND AGEまでご相談ください
50歳代から効率的に貯蓄するには?おすすめの資産運用方法

50歳から効率的に貯蓄を増やすには、預金のような元本保証の商品だけではなく、株式や投資信託などの「元本割れのリスクがあるが、高いリターンを期待できる商品」を組み合わせて運用していくことが大切です。
投資方法としては「積立投資」と「一括投資」の2通りがありますので、それぞれ紹介します。
積立投資
積立投資とは、一定の金額を定期的に投資していく方法です。「毎月2万円分の投資信託を買う」というような方法が積立投資にあたり、簡単に始めやすいことが特徴です。
また、投資信託や株は値動きがあり、価格が高い時期も安い時期もあります。積立投資であれば、毎月一定額を買い続けることになるため、投資のリスクを軽減できるというメリットがあります。
積立投資は、少額から始めやすいため、幅広い年齢の人に適しています。給与天引きなどで強制的に積み立てる仕組みを作ることで、毎月確実に積立を行い、運用できます。
一括投資
一括投資とは、まとまった金額を同じ時期に一括して投資することをいいます。一括投資では、短期的に見た場合は「高値掴み」のリスクがありますが、値動きが右肩上がりの金融商品の場合は、積立投資よりもリターンが高くなる傾向にあります。
ただ、積立投資に比べると、高値掴み・値下がりのリスクは大きくなりますし、損益の変動も大きいため、損益の上下が精神的なストレスになることもあります。
資産がマイナスに振れた場合、大きなストレスを感じてしまうという人は、積立投資をメインに運用すると良いでしょう。
50代以降の転職でお困りの方はBEYOND AGEまでご相談ください
50歳代でも間にあう!貯蓄にまわすお金を増やすコツ

50歳代から貯蓄を始めても遅いということはなく、しっかりと老後資金を貯めていけます。
貯蓄にまわせるお金がないという人は、今の家計を見直すなどして資金を捻出し、コツコツと貯めていきましょう。
ここでは、貯蓄にまわすお金を増やすコツを紹介します。
固定費の見直しをする
貯蓄にまわせるお金を捻出するための方法として、固定費を見直すことが効果的です。
家計における固定費とは、毎月定額・ほぼ定額でかかる支出のことをいい、以下のようなものがあります。
- 家賃や管理費、住宅ローン返済など住居に係る費用
- 水道・ガス・電気料金
- スマホ代や自宅のインターネット回線料金などの通信費
- 掛け捨ての生命保険・火災保険
- サブスクリプションサービス料
- 自動車のローンや駐車場代
固定費の見直し方としては、スマホは大手から格安スマホに変更する、保険関係を今の生活に合うものに見直す、利用していないサブスクを契約解除するという方法があります。
固定費を見直して減らした分を、毎月継続して貯蓄にまわすことで、しっかりと貯蓄を積み上げていくことができます。
家計簿をつける
毎月家計簿をつけて、収支を見える化するのも良い方法です。
無駄な支出はないと思っていても、家計簿に書き出してみると、節約できる項目が見つかることもあります。
趣味や娯楽は、生活を充実させるために欠かせないものですが、予想以上にお金を使っている場合もあるため、支出額をまずは確認してみましょう。
最近はノートタイプだけでなく、無料の家計簿アプリもたくさんありますので、自分に合う方法でこまめに家計簿をつけることをおすすめします。
ポイントを活用する
クレジットカードのポイント還元や、ドラッグストアやスーパーのポイントやクーポン券をうまく利用すると、家計を節約できます。
スマホにドラッグストアやスーパーのアプリを入れると、お得な情報が自動的に送られてくるので、うまく活用すると良いでしょう。
50代以降の転職でお困りの方はBEYOND AGEまでご相談ください
50歳代から収入を増やすことも考えよう

50歳からしっかりと貯蓄を増やしたい場合は、収入を増やすことも検討しましょう。節約でもある程度のお金は捻出できますが、節約しすぎると生活の質が必要以上に下がってしまいますし、ストレスになってしまうこともあります。
収入そのものを増やすことで、より多くのお金を貯蓄にまわせるようになります。50歳代から収入を増やす方法としては、以下のような方法があります。
- 副業収入を足して平均年収を増やす
- 独立・起業して収入を増やす
近年は副業可の企業も増えてきています。オンラインで仕事を受注したり、定時退社後や休日に別の仕事をするという方法がありますが、本業がおろそかになって評価や給与が下がるリスクがあるため、注意が必要です。
50代から副業を始めたい方は以下の記事を参考にしてみてください。
シニア世代の方々にとって、副業は収入源を確保する以上に重要な意味を持ちます。50代、60代になると、転職や役職定年、再雇用などにより収入が減少するケースが多々あります。 また、それらの状況の変化を通じて仕事へのやりがいを失う可能性も[…]
また、50歳から定年後まで、長い目で見て収入を増やしたい、仕事のやりがいを持ち続けたいという人は、独立・起業するのもひとつの方法です。
独立すると、「雇われる立場」から「自分が主体的に仕事をする立場になる」ため、モチベーションが高い状態で働き続けられます。
また、定年がないため、体調やライフイベントに合わせて働き方を柔軟に調整しながら、好きなだけ働き続けることが可能です。
50歳以降は役職定年や早期退職、また定年退職など、仕事の状況が大きく変わるタイミングともいえます。 なかには環境の変化を受けて仕事にやりがいを感じず、「自分らしい働き方を実現したい」と考える人もいるでしょう。 こちらの記事では[…]
50代以降の転職でお困りの方はBEYOND AGEまでご相談ください
まとめ
50歳代の貯蓄額は平均で1,611万円、中央値で745万円です。最も多いのは「貯蓄額が3,000万円以上」で、15.5%ですが、「100万円未満」という人も12.5%となっており、貯蓄額は個人によって大きな開きがあることがわかります。
50歳代は、老後に向けて資金を効率的に貯められる時期です。固定費の節約などで貯蓄にまわせるお金を捻出することが大切ですが、収入そのものを上げるという方法もあります。
50歳代は気力・体力ともに充実しており、さまざまな選択肢を選べる年代です。貯蓄をすることはもちろんのこと、長い目で見てどのような働き方をしていくのかということも、一度検討してみることをおすすめします。